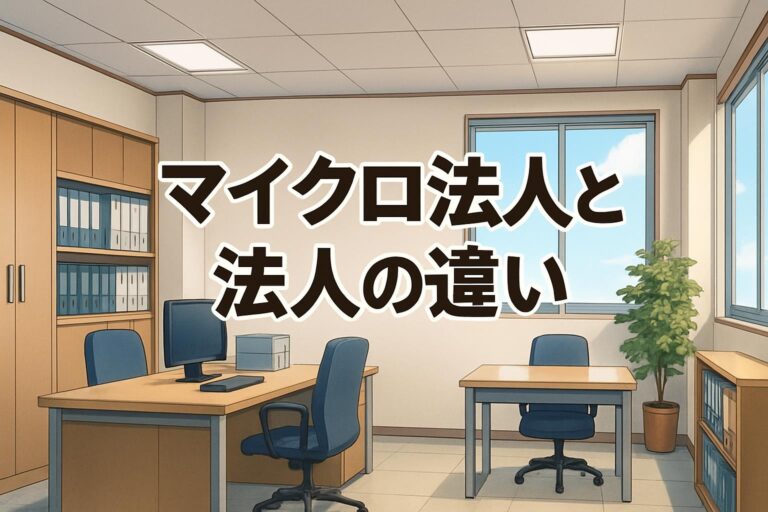マイクロ法人と一般的な法人の違いがわからず、設立で悩んでいませんか?
本記事では、設立費用・税金・社会保険料など7つの項目で両者を一覧表を用いて徹底比較。
それぞれのメリット・デメリットから、個人事業主や副業を持つ会社員など、あなたの状況に最適な選択肢がどちらなのかを明確に示します。
この記事を読めば、節税効果を最大化し、後悔しない法人形態を選べるようになります。
マイクロ法人と法人の基本的な違いを解説
「マイクロ法人」という言葉を耳にする機会が増え、個人事業主やフリーランス、副業を行う会社員の方々から大きな注目を集めています。
しかし、一般的な「法人」と何が違うのか、具体的に説明できる方は少ないのではないでしょうか。
この章では、マイクロ法人と法人の最も基本的な違いについて、それぞれの定義から掘り下げて解説します。
この章を読めば、両者の根本的な関係性を理解でき、今後の具体的な比較検討がスムーズに進むでしょう。
そもそもマイクロ法人とは?法律上の定義はない
まず最も重要な点として、「マイクロ法人」という言葉は法律上の正式な用語ではありません。
会社法などの法律どこにも、マイクロ法人の定義は存在しないのです。
一般的にマイクロ法人とは、社長一人、あるいは配偶者や親族などごく少人数の家族だけで経営する、非常に小規模な法人を指す「通称」です。
特に、個人事業主や副業所得のある方が、主に社会保険料の負担軽減や節税を目的として設立するケースで使われることが多い言葉です。
つまり、法律上の扱いは、後述する株式会社や合同会社といった一般的な法人と全く同じです。
あくまで、その規模や運営目的によって「マイクロ法人」と呼ばれているに過ぎません。
個人事業と法人を組み合わせた「二刀流」で事業を行う際に、法人側を指してマイクロ法人と呼ぶこともあります。
一般的な法人(株式会社・合同会社)とは
一方、「法人」とは、法律によって「人(自然人)」と同じように権利や義務が認められた組織のことです。
法人格を持つことで、組織名義で契約を結んだり、銀行口座を開設したり、財産を所有したりすることが可能になります。
日本で事業目的として設立される法人の形態にはいくつか種類がありますが、その代表格が「株式会社」と「合同会社」です。
マイクロ法人を設立する場合も、このどちらかの形態を選ぶのが一般的です。
それぞれの特徴を簡単に見てみましょう。
株式会社(Kabushiki Kaisha/KK)
株式会社は、株式を発行して出資者(株主)から資金を集めて事業を行う会社形態です。
日本で最も多く設立されている形態であり、社会的信用度が非常に高いのが最大の特徴です。
出資者である「株主」と、経営を行う「取締役」が分離されている(所有と経営の分離)のが原則ですが、中小企業では株主=取締役であるケースがほとんどです。
将来的に事業を大きくしたい、外部から資金調達をしたい、上場を目指したいといった場合に適しています。
合同会社(Godo Kaisha/GK)
合同会社は、2006年の会社法施行によって新設された比較的新しい会社形態です。
最大の特徴は、設立費用の安さと経営の自由度の高さにあります。
出資者全員が会社の経営者(業務執行社員)となり、意思決定を迅速に行うことができます。
Apple JapanやGoogleなど、外資系の有名企業が日本法人として合同会社の形態を選んでいる例も多くあります。
設立や運営のコストを抑え、スピーディーに事業を始めたい場合に適しています。
これら2つの法人の主な違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 社会的信用度 | 高い | 株式会社に比べるとやや低い傾向 |
| 出資者の名称 | 株主 | 社員 |
| 経営者の名称 | 取締役(代表取締役など) | 業務執行社員(代表社員など) |
| 意思決定機関 | 株主総会、取締役会 | 原則として社員全員の同意(総社員の同意) |
| 設立費用の目安 | 約20万円~ | 約6万円~ |
このように、マイクロ法人は特別な法人格ではなく、株式会社や合同会社といった一般的な法人を、個人レベルの小規模なスケールで運営する際の「呼び方」であると理解しておきましょう。
【一覧比較表】マイクロ法人と法人の違いを7つの項目でチェック
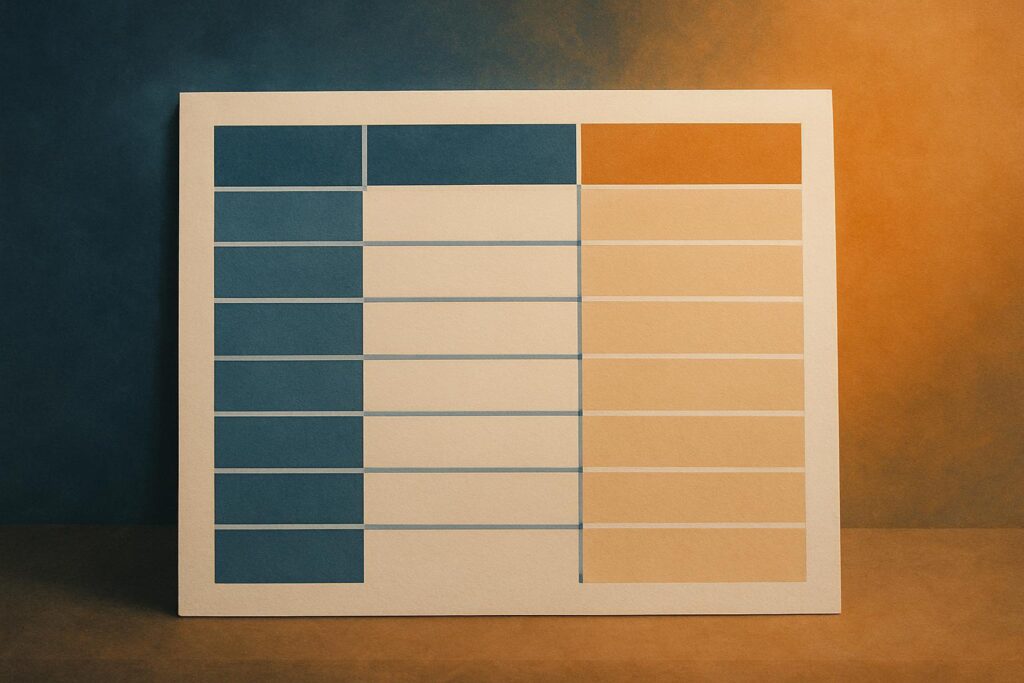
マイクロ法人と一般的な法人の違いは多岐にわたります。
ここでは、両者の特徴をより深く理解するために、「設立費用」「税金」「社会保険料」など、特に重要な7つの項目に絞って比較します。
まずは、全体像を把握できるよう、以下の比較表をご覧ください。
| 比較項目 | マイクロ法人 | 一般的な法人(株式会社など) |
|---|---|---|
| 設立費用 | 低い(合同会社なら約6万円~) | 高い(株式会社なら約20万円~) |
| 税金 | 役員報酬の調整で法人税を抑えやすい | 事業所得に応じて課税される |
| 社会保険料 | 役員報酬を低く設定し、負担を最小限にできる | 役員報酬や従業員の給与額に応じて高くなる |
| 役員・従業員 | 役員1名が基本。従業員は雇用しないことが多い | 複数の役員や従業員を雇用することが多い |
| 事業の自由度 | 個人事業との事業分離が必要 | 定款の範囲内で自由に事業展開が可能 |
| 社会的信用度 | 個人事業主よりは高いが、限定的 | 高い。融資や取引で有利 |
| 設立・維持の手間 | 法人として最低限の手間はかかる(決算申告など) | 事業規模に応じて事務負担が増加する |
この表で大枠を掴んだ上で、各項目の詳細を一つずつ見ていきましょう。
設立費用や資本金の違い
法人を設立する際には、定款の作成や登記申請のために法定費用がかかります。
この初期コストは、マイクロ法人と一般的な法人で大きく異なります。
一般的な法人として多く選ばれる株式会社の場合、定款認証手数料や登録免許税などで合計約20万円~25万円の費用が必要です。
一方、マイクロ法人では、設立費用を抑えられる合同会社が選ばれるのが一般的です。
合同会社は定款認証が不要なため、登録免許税の最低6万円(電子定款の場合)から設立でき、初期投資を大幅に削減できます。
また、資本金については、会社法の改正により株式会社・合同会社ともに1円から設立可能です。
しかし、資本金は会社の体力や信用度を示す指標の一つでもあります。
事業拡大を目指す一般的な法人ではある程度の資本金を用意することが多いですが、マイクロ法人の場合は事業規模が小さいため、資本金も数万円から数十万円程度に設定されるケースがほとんどです。
税金の種類と税率の違い
法人には、その所得に対して「法人税」「法人住民税」「法人事業税」といった税金が課せられます。
この基本的な税金の仕組みは、マイクロ法人も一般的な法人も同じです。
違いが生まれるのは、税率の適用です。資本金1億円以下の中小法人の場合、法人税率は所得が年800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。
マイクロ法人は、役員報酬を調整して法人の所得を低くコントロールすることが多いため、結果的に低い法人税率の恩恵を受けやすいという特徴があります。
また、法人設立後の消費税については、原則として資本金1,000万円未満であれば、設立から最大2年間は納税が免除される「事業者免税点制度」の対象となります。
これはマイクロ法人でも一般的な法人でも同様に適用されるルールです。
社会保険料の負担の違い
マイクロ法人を設立する最大の目的とも言えるのが、この社会保険料の最適化です。
法人を設立すると、たとえ社長1人であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。
一般的な法人では、役員や従業員に支払う給与(役員報酬)の金額に応じて社会保険料が決まるため、報酬が高額になるほど負担も増大します。
一方、マイクロ法人の場合、自身の役員報酬を社会保険料が最も安くなる水準(標準報酬月額の最低等級)まで意図的に低く設定します。
これにより、法人としての社会保険料の支払いを最小限に抑えることが可能です。
個人事業主として高い所得を得ている場合、所得に連動して国民健康保険料が高額になりますが、マイクロ法人を設立してこのスキームを活用することで、世帯全体での社会保険料負担を劇的に軽減できる可能性があります。
役員や従業員に関する違い
法人の組織構成にも違いが見られます。一般的な法人は、事業を成長させるために複数の役員を置いたり、多くの従業員を雇用したりすることが前提です。
それに対してマイクロ法人は、社会保険料の最適化や節税を主目的とするため、オーナー社長1人、もしくは生計を共にする家族を役員とするケースがほとんどです。
従業員を雇用すると、その従業員の社会保険料(会社負担分)や労働保険料の支払い義務が発生し、マイクロ法人のメリットが薄れてしまいます。
そのため、マイクロ法人では原則として従業員を雇用しません。外部の力が必要な場合は、業務委託契約を結び、外注パートナーとして協力してもらうのが一般的です。
事業の自由度や運営の違い
事業運営の柔軟性においても、両者には異なる側面があります。
一般的な法人は、定款で定めた事業目的の範囲内であれば、複数の事業を自由に展開し、事業拡大を目指すことができます。
一方で、マイクロ法人は個人事業主との両立が前提となることが多く、その場合は個人事業の事業内容とマイクロ法人の事業内容を明確に分ける必要があります。
例えば、「個人事業でライター業、マイクロ法人で不動産賃貸業」のように、所得の種類や事業実態が混同しないように管理しなければなりません。
これは、税務調査などで事業実態が一体であると判断された場合に、マイクロ法人設立のメリットが否認されるリスクを避けるためです。
意思決定のスピードに関しては、オーナー1人であるマイクロ法人が圧倒的に迅速です。
一般的な株式会社では、重要な決定に株主総会や取締役会の決議が必要になる場合があります。
社会的信用度の違い
法人格を持つことで、個人事業主よりも社会的信用度が高まるのは、マイクロ法人も一般的な法人も同じです。
しかし、その「信用度のレベル」には差があります。
株式会社などの一般的な法人は、しっかりとした事業計画や資本金、従業員数を背景に、金融機関からの融資や大手企業との取引、優秀な人材の採用において高い信用力を発揮します。
法人でなければ契約できない、といったケースも少なくありません。
マイクロ法人も法人であることに変わりはありませんが、資本金が少額で従業員もおらず、実質的な事業規模が小さいことから、一般的な法人ほどの高い信用度は得にくいのが実情です。
ただし、個人事業主と比較すれば、法人名義で契約や口座開設ができるため、信用度は一段階上がると言えるでしょう。
設立や維持の手間の違い
最後に、設立と維持にかかる事務的な手間についてです。
設立手続き(定款作成、登記申請など)は、どちらの法人形態であっても必要であり、専門的な知識が求められます。
違いが顕著になるのは、設立後の維持管理です。マイクロ法人も一般的な法人も、年に一度の決算と法人税の申告が義務付けられています。
これは個人事業主の確定申告よりもはるかに複雑で、税理士に依頼するのが一般的であり、その分の顧問料が発生します。
また、役員の任期が満了すれば変更登記が必要ですし、社会保険に関する手続きも定期的に発生します。
マイクロ法人は事業規模が小さいため、日々の経理処理の量は少ないかもしれませんが、法人として存続するために最低限必要な法務・税務の手間とコストは、一般的な法人と同様にかかることを理解しておく必要があります。
マイクロ法人を設立するメリットとデメリット

マイクロ法人には、個人事業主や一般的な法人とは異なる特有のメリットとデメリットが存在します。
特に、社会保険料や税金の面で大きな恩恵を受けられる可能性がある一方で、設立・運営の手間やコストも発生します。
ここでは、マイクロ法人を設立する際に知っておくべきメリットとデメリットを詳しく解説します。
マイクロ法人のメリット 社会保険料の最適化と節税効果
マイクロ法人を設立する最大のメリットは、社会保険料の負担を大幅に軽減できる可能性と、多様な節税スキームを活用できる点にあります。
個人事業主や会社員として高い所得を得ている方ほど、その効果は大きくなります。
社会保険料の負担を最適化できる
個人事業主が加入する国民健康保険料は、前年の所得に応じて算出され、上限額も比較的高く設定されています。
そのため、所得が増えるほど保険料の負担も重くなるのが一般的です。
一方、法人の役員が加入する健康保険・厚生年金保険(社会保険)の保険料は、役員報酬の金額(標準報酬月額)に基づいて決まります。
マイクロ法人では、この仕組みを利用して役員報酬を意図的に低く設定することで、社会保険料を最小限に抑えることが可能です。
例えば、個人事業で得た利益の大部分を法人に残し、自身は法人から最低限の役員報酬(例:月額45,000円など)だけを受け取る形にすれば、社会保険料の負担を劇的に下げることができます。
これは、マイクロ法人設立における最も強力なメリットと言えるでしょう。
| 項目 | 個人事業主の場合 | マイクロ法人を設立した場合 |
|---|---|---|
| 所得(利益) | 事業所得800万円 | 個人事業の所得は法人へ。役員報酬は年間60万円(月5万円) |
| 加入する保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金保険 |
| 保険料の基準 | 前年の事業所得 | 役員報酬額(標準報酬月額) |
| 年間の保険料負担(概算) | 約120万円(自治体により変動) | 約17万円 |
| 特徴 | 所得が増えるほど保険料も高くなる。上限あり。 | 役員報酬を低く設定することで、保険料をコントロールできる。 |
※上記はあくまで一例の概算です。実際の保険料は、お住まいの自治体や年齢、家族構成などによって異なります。
税金面でのメリットが大きい
マイクロ法人は、税金面でも多くのメリットを享受できます。
- 給与所得控除の適用
法人から受け取る役員報酬は給与所得となり、給与所得控除が適用されます。これは、事業所得にはない控除であり、課税対象となる所得を減らす効果があります。 - 所得の分散による税率の抑制
個人事業の所得は、所得税の累進課税(所得が高いほど税率が上がる仕組み)が適用されます。事業の利益を法人に移すことで、個人の高い所得税率を回避し、比較的低い法人税率の適用を受けることができます。 - 経費(損金)にできる範囲が広がる
法人化することで、経費として認められる範囲が個人事業主よりも広がります。例えば、役員社宅制度を利用して家賃の一部を経費にしたり、出張手当(日当)を非課税で支給したり、生命保険料の一部を損金算入したりといった節税策が可能になります。 - 消費税の免税事業者になれる可能性がある
資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除されます(インボイス制度への登録状況など、一定の要件があります)。
マイクロ法人のデメリット 事務負担の増加と運営コスト
メリットが大きい一方で、マイクロ法人には無視できないデメリットも存在します。
特に、これまで個人事業主として活動してきた方にとっては、事務的な負担やコストの増加が大きな壁となる可能性があります。
設立・運営に関する事務負担が大きい
個人事業主が開業届を出すだけで始められるのに対し、法人の設立には複雑な手続きが必要です。
定款の作成・認証、法務局への法人登記など、専門的な知識が求められるため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
また、設立後も以下のような事務作業が常に発生します。
- 会計処理・決算申告
個人事業主の簡易な帳簿付けとは異なり、法人は複式簿記による厳密な会計処理が義務付けられています。年に一度の決算と法人税の申告は非常に複雑で、多くの場合、税理士への依頼が必須となります。 - 社会保険の手続き
法人を設立すると、たとえ社長一人であっても社会保険への加入が義務となります。加入手続きや毎月の保険料の計算・納付、年度更新などの手続きが必要です。 - 税務関連の各種手続き
源泉所得税の納付や年末調整、法定調書の作成・提出など、個人事業主にはなかった税務手続きが発生します。
これらの事務作業をすべて自分で行うのは現実的ではなく、税理士や社会保険労務士といった専門家への依頼費用が発生する
ことを念頭に置く必要があります。
赤字でもコストが発生する
マイクロ法人のもう一つの大きなデメリットは、事業が赤字であっても必ず発生するコストがある点です。
- 法人住民税の均等割
法人は、利益が出ていなくても、事業所を置く自治体に対して法人住民税の「均等割」を納める義務があります。これは資本金の額や従業員数によって決まり、最低でも年間7万円程度の負担が発生します。 - 専門家への報酬
前述の通り、決算申告を税理士に依頼する場合、顧問料や決算料として年間数十万円のコストがかかります。これも事業の損益に関わらず発生する固定費です。
これらの維持コストは、マイクロ法人を運営し続ける限り毎年発生します。
社会保険料の削減額や節税効果が、これらの運営コストを上回るかどうかを設立前に慎重にシミュレーションすることが、マイクロ法人で失敗しないための重要なポイントです。
一般的な法人を設立するメリットとデメリット

マイクロ法人と比較して、一般的な法人(株式会社や合同会社など)は、事業規模の拡大を目指す際に多くのメリットを享受できます。
しかし、その反面、設立や維持にかかるコストや手間も大きくなります。
ここでは、一般的な法人を設立するメリットとデメリットを詳しく解説します。
法人のメリット 高い社会的信用と資金調達のしやすさ
法人化がもたらす最大のメリットは、個人事業主とは比較にならないほどの社会的信用の高さです。
これが、事業を成長させる上での様々な好影響につながります。
高い社会的信用度
法人は、法務局に設立登記を行うことで正式に成立します。
商号(会社名)、本店所在地、役員、資本金といった情報が公開されるため、透明性が高く、社会的な信用を得やすいのが特徴です。
この信用度の高さは、以下のような場面で大きなアドバンテージとなります。
- 取引先の拡大:特に大企業は、コンプライアンスの観点から個人事業主との取引を避け、法人とのみ契約するケースが少なくありません。法人化することで、ビジネスチャンスが大きく広がります。
- 人材の採用:求職者にとって、社会保険が完備され、経営基盤が安定している印象のある法人は、個人事業主よりも魅力的に映ります。優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。
- 不動産契約:事務所や店舗を借りる際の賃貸契約においても、法人のほうが審査に通りやすい傾向があります。
資金調達の選択肢の広さ
社会的信用が高い法人は、金融機関からの評価も高くなるため、資金調達がしやすくなります。
個人事業主の場合、融資は事業主個人の信用力に大きく依存しますが、法人は事業そのものの将来性や収益性で評価されます。
日本政策金融公庫や地方自治体の制度融資に加え、民間の金融機関からのプロパー融資も受けやすくなります。
さらに、株式会社であれば、株式を発行して投資家から出資を募る「エクイティ・ファイナンス」という選択肢も生まれます。
これは、事業の急成長を目指す上で非常に強力な資金調達手段です。
優れた節税効果
法人は、個人事業主よりも経費として認められる範囲が広く、多様な節税策を活用できます。
- 役員報酬:自身への給与を「役員報酬」として経費計上できます。役員報酬は給与所得控除の対象となるため、所得税の負担を軽減できます。
- 退職金の活用:役員に退職金を支払うことができ、これは損金として算入可能です。受け取る側も退職所得控除という大きな税制優遇を受けられます。
- 生命保険料の経費化:一定の条件を満たすことで、法人が契約する生命保険の保険料を経費として計上できます。
- 欠損金の繰越控除:事業で生じた赤字(欠損金)を、翌年以降の黒字と相殺できる期間が10年間あります(個人事業主は3年間)。
有限責任であること
株式会社や合同会社は「有限責任」です。
これは、万が一事業が失敗して倒産した場合でも、経営者の責任は出資した金額の範囲内に限定されることを意味します。
個人の資産まで差し押さえられる「無限責任」の個人事業主と比べて、リスクを抑えて事業に挑戦できる点は大きなメリットです。
法人のデメリット 設立や維持にかかるコストの高さ
多くのメリットがある一方で、法人は設立時にも設立後にも、個人事業主やマイクロ法人に比べて多くのコストと手間がかかります。
設立費用がかかる
法人の設立には、定款の認証や登記申請の際に法定費用(実費)が必要です。
専門家(司法書士など)に依頼する場合は、さらに手数料が上乗せされます。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 0円(電子定款の場合) | 0円(電子定款の場合) |
| 定款認証手数料 | 3万円~5万円 | 不要 |
| 登録免許税 | 資本金の0.7%(最低15万円) | 資本金の0.7%(最低6万円) |
| 合計(最低額) | 約20万円~ | 約6万円~ |
このように、最もシンプルな合同会社でも最低6万円、一般的な株式会社では20万円以上の初期費用が発生します。
赤字でも発生する維持コスト
法人を維持していくためには、たとえ事業が赤字であっても支払い義務のあるコストが存在します。
- 法人住民税の均等割:法人は、利益の有無にかかわらず、資本金や従業員数に応じて法人住民税の「均等割」を納付する義務があります。最低でも年間約7万円の税金が発生するため、これは大きな負担となり得ます。
- 社会保険料の負担:法人は、役員1人であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。保険料の約半分を会社が負担する必要があり、これは固定費として重くのしかかります。
- 税理士への顧問料:法人の決算申告は非常に複雑なため、税理士に依頼するのが一般的です。顧問契約を結ぶ場合、年間で数十万円の費用がかかります。
事務負担の増加
法人は、個人事業主と比較して、経理や税務、法務に関する事務手続きが格段に複雑化・増加します。
会計処理は複式簿記が必須となり、厳格なルールに則って行う必要があります。
また、決算申告だけでなく、役員変更や本店移転などがあった際には、その都度、法務局への変更登記手続きと登録免許税の支払いが必要です。
これらの事務手続きを怠るとペナルティが課される可能性もあるため、専門知識を持つ人材や外部専門家のサポートが不可欠です。
お金の使い方が制限される
個人事業主は事業で得た利益を自由に使えますが、法人の場合、会社のお金と個人のお金は明確に区別されます。
経営者であっても、会社のお金を個人的な目的で自由に引き出すことはできず、「役員報酬」という決められた形で受け取る必要があります。
役員報酬の金額は事業年度の途中で自由に変更できないなど、資金の流動性が低い点もデメリットと言えるでしょう。
あなたはどっち?マイクロ法人と法人の選び方

ここまでマイクロ法人と一般的な法人の違いを様々な角度から比較してきました。
しかし、「違いは分かったけれど、結局自分はどちらを選べばいいのか?」と悩んでいる方も多いでしょう。
この章では、あなたの事業目的や将来のビジョンに合わせて、最適な選択ができるよう具体的なケースを挙げて解説します。
どちらの形態が優れているというわけではなく、あなたの状況によって最適な選択は異なります。
以下の判断基準を参考に、ご自身のケースに当てはめて考えてみましょう。
| 判断軸 | マイクロ法人がおすすめ | 一般的な法人がおすすめ |
|---|---|---|
| 主な目的 | 社会保険料の最適化・個人の節税 | 事業の拡大・大規模な資金調達・人材採用 |
| 事業規模 | 個人または家族経営のスモールビジネス | 中規模〜大規模、多店舗展開や支社設立を想定 |
| 働き方 | 個人事業主との兼業(二刀流)・会社員の副業 | 事業に専念・複数人の従業員を雇用 |
| 将来の展望 | 現状の所得を維持しつつ手残りを最大化したい | 上場(IPO)や事業売却(M&A)も視野に入れている |
マイクロ法人の設立がおすすめな人
マイクロ法人の設立は、特に「個人の税金や社会保険料の負担を最適化したい」と考えている方に大きなメリットがあります。
事業を大きくするというよりは、現在の収入を維持しながら手元に残るお金を最大化する戦略です。
個人事業主と両立して節税したい人
フリーランスのエンジニアやデザイナー、コンサルタントなど、個人事業主としてすでに高い所得を得ている方は、マイクロ法人の設立が有力な選択肢となります。
個人事業主の所得が増えると、所得税の累進課税や国民健康保険料の負担が重くのしかかります。
そこで、マイクロ法人を設立し、個人事業とは別の事業を法人で行う「二刀流」という手法が有効です。
具体的には、マイクロ法人から自身に低い役員報酬(例:月額45,000円など)を設定し、その報酬額に基づいて法人の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
これにより、個人事業の高い所得に基づいて算出される高額な国民健康保険料を、法人の低い役員報酬を基準とした社会保険料に抑えることが可能になります。
さらに、所得を個人事業と法人に分散させることで、所得税率を低く抑える効果も期待できます。
副業の所得が大きい会社員
会社員として給与所得を得ながら、副業で年間数百万円といった大きな所得がある方もマイクロ法人の設立を検討する価値があります。
通常、副業で得た所得(事業所得や雑所得)は、本業の給与所得と合算して確定申告するため、所得税や住民税の負担が大きくなります。
しかし、副業部分を法人化することで、その収入を個人の所得ではなく法人の売上として計上できます。
法人から自分へ役員報酬として給与を支払う形にすれば、給与所得控除が適用されるため、同じ収入額でも課税所得を圧縮できるメリットがあります。
また、法人税率は所得が一定額を超えると個人の所得税率よりも低くなるため、所得が大きいほど節税効果は高まります。
自宅の家賃や通信費の一部を法人の経費として計上しやすくなる点も魅力です。
一般的な法人の設立がおすすめな人
一方で、個人の節税メリットよりも事業そのものの成長や拡大を最優先に考えるのであれば、一般的な法人(株式会社や合同会社)の設立が適しています。
社会的信用を武器に、ビジネスをスケールさせていくための土台となります。
事業を大きく拡大していきたい人
将来的に事業を大きく成長させ、売上数十億円規模や従業員数十人規模を目指すのであれば、迷わず一般的な法人を選ぶべきです。
法人格、特に株式会社は社会的な信用度が最も高い形態です。
この信用力は、ビジネスの様々な場面で有利に働きます。
例えば、金融機関からの融資やベンチャーキャピタルからの出資といった大規模な資金調達が、個人事業主やマイクロ法人に比べて格段に行いやすくなります。
また、大手企業との取引(BtoB)では、契約相手が法人であることが条件となるケースも少なくありません。
法人格を持つことで、ビジネスチャンスを逃すことなく、事業拡大のスピードを加速させることができます。
従業員を雇用する予定がある人
自分一人や家族だけでなく、従業員を雇用してチームで事業を成長させていきたいと考えている場合も、一般的な法人の設立がおすすめです。
法人には社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。
これは一見コスト増に見えますが、採用活動においては大きな強みとなります。
社会保険が完備されていることは、求職者が企業を選ぶ上での重要な判断基準であり、優秀な人材を確保しやすくなるからです。
個人事業主でも従業員5名以上で社会保険の加入義務は生じますが、法人であれば最初から整備されているため、求職者に安心感を与えられます。
さらに、退職金制度の導入や福利厚生の充実など、従業員が長く働きたいと思える環境を整えやすいのも法人のメリットです。
しっかりとした組織体制を築き、事業の永続性を目指すのであれば、法人設立が最適な選択と言えるでしょう。
マイクロ法人設立で失敗しないための注意点

マイクロ法人は、社会保険料の最適化や節税など、多くのメリットが期待できる魅力的な選択肢です。
しかし、そのメリットを最大限に享受するためには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。
知識がないまま設立を進めてしまうと、かえって税務上のリスクを負ったり、余計なコストが発生したりする可能性があります。
ここでは、マイクロ法人設立で失敗しないための2つの重要なポイントを詳しく解説します。
個人事業との事業内容を明確に分ける
個人事業主がマイクロ法人を設立する場合、最も注意すべき点が「個人事業と法人事業の分離」です。
もし税務署から「実質的に同一の事業である」と判断された場合、「租税回避行為」とみなされ、マイクロ法人設立のメリットがすべて失われるリスクがあります。
これを「事業一体性の否認」と呼びます。具体的には、マイクロ法人の所得が個人事業の所得と合算され、結果的に社会保険料の負担が増えたり、消費税の免税事業者としてのメリットが受けられなくなったりします。
このような事態を避けるため、客観的に見て誰もが別の事業だと判断できるよう、事業内容を明確に分けることが不可欠です。
具体的にどのように事業を分離すればよいか、以下の表で確認しましょう。
| 項目 | リスクの低い分け方(良い例) | リスクの高い分け方(悪い例) |
|---|---|---|
| 事業内容 | 個人事業でWebライター、マイクロ法人で不動産賃貸業のように、全く異なる業種・事業ドメインにする。 | 個人事業でWebデザイン、マイクロ法人でWebサイト制作のように、業務内容が酷似・関連している。 |
| 取引先 | 個人事業の取引先とマイクロ法人の取引先が完全に異なる。 | 売上の大部分を占める主要な取引先が、個人事業とマイクロ法人で重複している。 |
| 資産・経理管理 | 事業用の銀行口座、会計帳簿、契約書、請求書などを完全に別々で管理している。 | 事業用の口座を分けておらず、経費の区別が曖昧になっている。 |
| 事務所・連絡先 | ホームページや名刺、電話番号などをそれぞれ別に用意し、外部から見ても別事業であることが明確になっている。 | ホームページや名刺に両方の事業内容を記載しており、実質的に一体の事業として運営している。 |
特に事業内容の選定は重要です。
個人事業の売上の一部をマイクロ法人に移すだけ、といった形式的な分離は最も危険です。
税務調査で指摘されないよう、設立段階から事業の分離を徹底しましょう。
役員報酬の設定は慎重に行う
役員報酬の金額設定は、社会保険料を最適化する上で最も重要な要素です。
健康保険料や厚生年金保険料は、役員報酬の金額に応じて決まる「標準報酬月額」を基準に算出されます。
そのため、役員報酬を低く設定すれば、社会保険料の負担を大幅に軽減できるのです。
一般的には、社会保険料が最低等級となる金額に役員報酬を設定するケースが多く見られます。
ただし、役員報酬を低く設定することにはデメリットもあるため、慎重な判断が求められます。
役員報酬設定のポイントと注意点
- 社会保険料の最低等級を狙う
役員報酬を低く抑えることで、法人として負担する社会保険料を最小化できます。具体的な金額は年度によって改定される可能性があるため、必ず日本年金機構などが公表している最新の保険料額表を確認してください。 - 将来の年金額が減少するデメリットを理解する
厚生年金保険料の支払額が少なくなるということは、将来受け取れる老齢厚生年金の受給額も少なくなることを意味します。iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)などを活用し、個人で老後資金を準備する計画も併せて検討することが重要です。 - 役員報酬は簡単に変更できない
法人税法上、役員報酬は「定期同日給与」として、原則として事業年度を通じて毎月同額を支払う必要があります。金額を変更できるのは、事業年度開始から3ヶ月以内のタイミングに限られます。一度設定すると1年間は変更できないため、個人事業の所得なども考慮した上で、無理のない資金繰りができる金額を設定しましょう。 - 生活費とのバランスを考える
マイクロ法人からの役員報酬だけで生活費を賄うのは現実的ではありません。あくまで社会保険料を最適化するための手段と割り切り、主な生活費は個人事業の所得から得るという資金計画を立てる必要があります。
これらの注意点を十分に理解し、専門家である税理士や社会保険労務士に相談しながら進めることで、マイクロ法人設立の失敗リスクを大幅に減らすことができるでしょう。
まとめ
マイクロ法人と一般的な法人の違いは、設立目的と事業規模にあります。
マイクロ法人は法律上の区分ではなく、主に社会保険料の最適化や節税を目的とした一人法人を指し、個人事業主や副業所得の大きい会社員におすすめです。
一方、一般的な法人は事業の拡大を目指し、高い社会的信用や資金調達のしやすさがメリットです。
ご自身の事業計画や目的に応じて、設立費用、税金、運営コストなどを総合的に比較し、最適な法人形態を選択することが重要です。