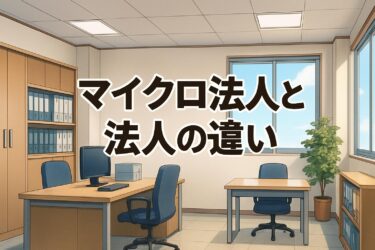法人成り後も個人事業を残す「二刀流」は、所得分散による節税など大きなメリットがありますが、安易な判断は禁物です。
税務調査で所得移転を疑われたり、社会保険料の負担が増えたりするリスクも潜んでいます。
本記事では、個人事業を残すための明確な条件から、税金・社会保険で失敗しないための具体的な注意点までを網羅的に解説。
メリットを最大限に活かし、デメリットを回避するための知識がすべてわかります。
法人成りしても個人事業を残すことはできるのか
結論から申し上げると、法人成りをした後も、個人事業を残して「法人」と「個人事業主」の二刀流で事業を続けることは可能です。
法律上、法人の代表者が個人事業を営むことを禁止する規定はありません。
一般的に「法人成り」というと、個人事業のすべてを新しく設立した法人に引き継ぐことをイメージされる方が多いかもしれません。
しかし、実際には一部の事業だけを法人化し、残りの事業は引き続き個人事業として運営するという選択もできます。
この方法は、うまく活用すれば節税などのメリットを享受できる可能性がありますが、一方で安易に行うと税務署から厳しい指摘を受けるリスクも伴います。
そのため、二刀流を成功させるには、その条件と注意点を正確に理解しておくことが不可欠です。
法人と個人事業主の二刀流が認められる条件
法人と個人事業主の二刀流が税務上認められるためには、単に形式を分けるだけでなく、それぞれの事業が独立しており、取引に合理性があることを客観的に証明できる必要があります。
税務署が最も問題視するのは、この仕組みが「不当な租税回避行為」にあたらないかという点です。
具体的には、以下の条件を満たしていることが重要になります。
| 条件 | 具体的な内容 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 事業の明確な区分 | 法人と個人で営む事業内容が明確に異なり、それぞれが独立して運営されていること。 | 区分が曖昧だと、実質的に一つの事業と見なされ、所得を不当に分散させている(所得移転)と疑われる原因になります。 |
| 取引価格の適正性 | 法人と個人の間で取引を行う場合、その価格が第三者と取引する際の市場価格(時価)であること。 | 法人から個人へ不当に安く業務を発注するなど、意図的な利益操作を防ぐためです。 |
| 経費の明確な按分 | 事務所の家賃や通信費など、共通で発生する経費は、事業の実態に応じた合理的な基準(例:使用面積比、業務時間比など)で按分されていること。 | 恣意的な経費計上を防ぎ、それぞれの事業で発生した費用を正しく計上していることを示すためです。 |
| 独立した管理体制 | 銀行口座、会計帳簿、契約書などを法人と個人で明確に分けて管理していること。 | 資金や経理が混在していると、事業の実態が一体であると判断されやすくなります。 |
これらの条件を満たせず、税務調査で「実質的に同一事業」と判断された場合、個人事業の所得を法人の所得に合算して課税されたり、消費税の免税が取り消されたりといったペナルティが課される可能性があります。
事業内容を明確に区分することが大前提
前述の条件の中でも、「事業内容の明確な区分」は、二刀流を検討する上での絶対的な大前提です。
この区分が曖昧なままでは、他の条件をどんなに整えても、税務調査で指摘を受けるリスクは非常に高くなります。
事業を区分する際は、誰が見ても「これは別の事業だ」と納得できるような客観的な基準を設けることが重要です。
単に売上を分けるためだけの形式的な区分は認められません。
| 観点 | 適切な区分例(認められやすい) | 不適切な区分例(否認リスクが高い) |
|---|---|---|
| 事業の種類 | 法人は「Webシステム開発事業」、個人は「Webコンテンツのライティング事業」のように、提供するサービスや商品が明確に異なる。 | 法人も個人も同じ「Webデザイン事業」。売上規模に応じて請求元を法人と個人に振り分けている。 |
| ターゲット顧客 | 法人は「法人向けのコンサルティング」、個人は「個人向けのオンラインサロン運営」など、ターゲットとする顧客層が全く違う。 | 同じ顧客に対して、ある契約は法人名義で、別の契約は個人名義で締結している。 |
| 資産・設備の管理 | 法人の事業で使うPCやソフトウェアは法人名義で購入・契約し、個人の事業で使うものは個人名義で用意している。 | 同じ事務所、同じPCや機材を法人と個人で共用しており、経費の按分基準も曖昧。 |
もし、現在行っている事業を法人と個人に分けたいと考えているのであれば、まずは事業内容を客観的に切り分けることができるか、慎重に検討することから始めましょう。
この区分に自信が持てない場合は、安易に進めるのではなく、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
法人成りで個人事業を残す3つのメリット

法人成り後もあえて個人事業を残す「二刀流」という選択。手続きの煩雑さは増しますが、それを上回る大きなメリットが存在します。
特に税金面での恩恵は大きく、事業全体のキャッシュフローを改善する可能性を秘めています。
ここでは、法人成りで個人事業を残すことで得られる3つの主要なメリットを、具体的なポイントとともに詳しく解説します。
メリット1 所得分散による節税効果
法人成りで個人事業を残す最大のメリットは、所得を法人と個人に分散させることによる強力な節税効果です。
日本の所得税は、所得が高くなるほど税率も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
そのため、一つの事業体に所得が集中すると、高い税率が適用されてしまい、税負担が重くなりがちです。
そこで、事業を法人と個人に分け、所得を分散させます。
法人からは役員報酬として給与所得を受け取り、個人事業でも事業所得を得る形です。
これにより、法人と個人のそれぞれで所得が計算されるため、適用される所得税率を低く抑えることが可能になります。
さらに、法人から受け取る役員報酬には「給与所得控除」が適用され、個人事業の所得には「青色申告特別控除」が適用されるため、両方の控除を最大限に活用できる点も大きな魅力です。
結果として、個人事業主としてすべての所得を得る場合に比べて、トータルの税負担を大幅に軽減できるのです。
具体的に、課税所得1,500万円の場合でシミュレーションしてみましょう。
| 個人事業主のみの場合 | 法人と個人事業に分散した場合 | |
|---|---|---|
| 個人事業の課税所得 | 1,500万円 | 700万円 |
| 法人の所得(役員報酬支払前) | – | 800万円 |
| 個人の給与所得(役員報酬) | – | 800万円 |
| 個人の合計課税所得 | 1,500万円 | 約1,316万円 (給与所得控除後) |
| 個人の所得税・住民税(概算) | 約570万円 | 約475万円 |
| 法人の法人税等(概算) | – | 約185万円 |
| 合計税負担(概算) | 約570万円 | 約660万円 ※ただし、社会保険料負担が増えるため、単純比較はできない点に注意 |
※上記は各種控除や社会保険料を簡略化したシミュレーションです。実際には、法人税や社会保険料の負担も考慮する必要がありますが、所得を分散することで個人の税率をコントロールできるという仕組みをご理解ください。最適な所得のバランスは、事業内容や家族構成によって異なるため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。
メリット2 消費税の免税事業者でいられる可能性
消費税の納税義務は、原則として「基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているか」で判定されます。
法人と個人事業主はそれぞれ別の事業者として扱われるため、この判定も別々に行われます。
この仕組みを利用し、事業を法人と個人にうまく分割して、それぞれの課税売上高を1,000万円以下に抑えることができれば、法人と個人事業の両方で消費税の免税事業者であり続けることが可能です。
例えば、これまで個人事業で1,800万円の課税売上高があった場合、法人成りして事業を分割し、法人で900万円、個人事業で900万円の売上とすれば、どちらも納税義務の基準を下回ることになります。
また、新しく設立した法人は、原則として設立から最大2事業年度は消費税の納税が免除されます(資本金1,000万円未満などの条件あり)。
この免税期間のメリットを享受しつつ、個人事業も免税事業者のままでいられれば、事業全体として大きな節税につながります。
ただし、2023年10月から開始されたインボイス制度には注意が必要です。
取引先が課税事業者であり、仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の発行を求めてくる場合、免税事業者のままではインボイスを発行できません。
免税事業者でいることのメリットと、インボイスを発行できないことによるビジネス上のデメリットを天秤にかけ、慎重に判断する必要があります。
メリット3 小規模企業共済などを継続できる
個人事業主が加入できる有利な制度の中には、法人成りすると加入資格を失ったり、立場が変わったりするものがあります。
しかし、個人事業を残しておくことで、これらの制度を継続できるというメリットがあります。
代表的な制度が「小規模企業共済」です。これは、個人事業主や小規模企業の役員のための「経営者の退職金制度」ともいえるもので、掛金が全額所得控除の対象となるため、非常に高い節税効果があります。
通常、法人成りすると個人事業主としての立場は失われるため、一度解約し、法人の役員として再加入する手続きが必要です。
しかし、個人事業を残しておけば、個人事業主としての立場で小規模企業共済を継続でき、その掛金を個人事業の所得から控除し続けることができます。
役員としても加入条件を満たせば、法人と個人の両方で加入することも理論上は可能ですが、掛金の上限があるため、制度をよく理解した上での活用が求められます。
同様に、取引先の倒産に備える「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」も、掛金を事業の必要経費に算入できる節税効果の高い制度です。
これも個人事業を残すことで、個人事業としての加入を継続することが可能です。
これらの共済制度を有効活用し、将来への備えと節税を両立できる点は、二刀流ならではの大きな利点と言えるでしょう。
デメリットも確認 法人成りで個人事業を残す際の注意点

法人成り後も個人事業を残す「二刀流」は、所得分散による節税など多くのメリットが期待できる一方で、見過ごすことのできないデメリットや注意点が存在します。
メリットの恩恵を最大限に受けるためにも、事前にリスクを正確に把握し、対策を講じることが不可欠です。
安易な判断は、かえって手間やコストを増大させ、最悪の場合、税務署から指摘を受ける事態にもなりかねません。
ここでは、特に注意すべき2つの大きなデメリットについて詳しく解説します。
経理や事務手続きの負担が倍増する
法人と個人事業主の2つの事業体を運営するということは、経理や事務手続きが単純に2倍になる、あるいはそれ以上に複雑化することを意味します。
これまで個人事業主として一人で完結できていた業務も、二刀流になることで管理コストが大幅に増加する可能性があります。
具体的には、以下のような負担増が考えられます。
- 会計帳簿の分離:法人用と個人事業用の会計帳簿をそれぞれ作成・管理する必要があります。会計ソフトも別々に契約するか、事業所を追加するなどの対応が求められます。
- 確定申告の手間:法人は「法人税の確定申告」、個人は「所得税の確定申告」と、年に2回の異なる種類の税務申告が必要になります。決算期と個人の確定申告時期が異なれば、年間を通じて申告業務に追われることにもなりかねません。
- 請求・支払業務の厳格な区分:請求書や領収書、契約書などの書類は、法人名義と個人事業主名義のものを明確に使い分ける必要があります。取引先とのやり取りで混同が生じると、後々の経理処理が非常に煩雑になります。
- 資金管理の徹底:法人の銀行口座と個人事業用の銀行口座は、完全に分けて管理しなければなりません。プライベートの資金との区別はもちろん、法人と個人の間での安易な資金移動は、役員貸付金や役員借入金として処理する必要があり、会計処理を複雑にする要因となります。
これらの手続きを一覧で比較すると、その負担の大きさがより明確になります。
| 項目 | 法人 | 個人事業 |
|---|---|---|
| 会計帳簿 | 複式簿記での記帳が義務 | 青色申告(65万円控除)の場合、複式簿記が必須 |
| 決算・申告 | 法人税の確定申告(原則として事業年度終了後2ヶ月以内) | 所得税の確定申告(毎年2月16日~3月15日) |
| 主な税金 | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税など | 所得税、住民税、個人事業税、消費税など |
| 資金管理 | 法人名義の口座で厳格に管理 | 事業用口座とプライベート用口座の明確な分離が必要 |
これらの業務をすべて一人でこなすのは現実的ではなく、税理士などの専門家へ依頼する必要が出てくるでしょう。
その場合、法人と個人事業の両方の顧問料が発生するため、節税効果以上に専門家への報酬コストがかさんでしまうケースも十分に考えられます。
税務調査で厳しく見られる可能性がある
法人成りで個人事業を残す場合に最も警戒すべきなのが、税務調査です。
税務署は、一つの事業体が法人と個人に分かれているケースに対して、「意図的な利益操作や租税回避行為が行われていないか」という厳しい視点で調査を行います。
特に、以下の点は重点的にチェックされるポイントです。
- 所得移転の疑い:例えば、利益が多く出ている法人から、赤字状態の個人事業へ実態に見合わない高額な外注費を支払うといった行為は、法人の利益を個人に移転させ、法人税の負担を不当に軽くするための利益操作(所得移転)と見なされる可能性があります。
- 経費の付け替え:本来は法人が負担すべき経費(例:法人の事業で使う備品の購入費)を個人事業の経費として計上したり、その逆を行ったりする経費の付け替えも厳しくチェックされます。プライベートな支出を事業経費にすることと同様に、不適切な経理処理と判断されます。
- 事業実態の合理性:法人と個人の事業内容が酷似している、あるいは明確に区分されていない場合、「なぜ2つの事業体に分ける必要があるのか」という事業の合理性を問われます。合理的な理由を説明できなければ、法人と個人は実質的に一体の事業であると判断され、個人事業の売上や経費が法人のものとして合算されてしまう(否認される)リスクがあります。この場合、想定していた節税メリットが失われるだけでなく、追徴課税や加算税といった重いペナルティが課される恐れもあります。
このように、経理・事務手続きの煩雑化と税務調査のリスクは、法人成りで個人事業を残す際の二大デメリットと言えます。
これらのリスクを回避するためには、次の章で解説する税金や社会保険に関する具体的な対策を正しく理解し、実行していくことが極めて重要になります。
【税金編】法人成りで個人事業を残す場合に最も注意すべきこと

法人成り後も個人事業を残すという選択は、所得分散による節税など多くのメリットが期待できます。
しかし、その一方で税務上のリスクも伴います。
特に税務調査では、法人と個人事業主(実質的には同一人物)との関係性が厳しくチェックされる傾向にあります。
ここでは、追徴課税などの思わぬペナルティを避けるために、税金面で最も注意すべき2つのポイントを具体的に解説します。
所得移転を疑われないための対策
税務署が最も問題視するのは、法人の利益を不当に個人事業へ移転させる「所得移転」です。
これは意図的な利益操作による租税回避行為(脱税)とみなされる可能性が非常に高い行為です。
特に、代表者個人と法人が取引を行う場合、その取引条件を自由に設定しやすいため、税務調査の格好のターゲットとなります。
所得移転を疑われないためには、客観的で合理的な根拠に基づいた取引と経費計上が不可欠です。
法人と個人間の取引価格の適正性
法人と個人事業の間で業務委託契約を結んだり、個人所有の不動産を法人が借りたりといった取引が発生することがあります。
このとき、取引価格が「適正な時価」であることが絶対条件です。
例えば、法人が個人事業主であるあなたにコンサルティング業務を委託し、その対価として高額な業務委託料を支払ったとします。
もしその金額が、第三者の同業者に依頼した場合の相場よりも著しく高ければ、法人の利益を個人に移すための不当な取引(利益供与)と判断されかねません。
その結果、高額な部分は経費として認められず(損金不算入)、法人税の追徴課税を受けるリスクがあります。
このような事態を避けるためには、以下の対策が有効です。
- 業務委託料:契約書を必ず作成し、業務内容や成果物を明確にする。可能であれば、同業他社の料金表や相見積もりを取得し、価格の妥当性を証明できる資料を保管しておく。
- 不動産賃料:法人が個人所有の事務所や店舗を借りる場合は、近隣の類似物件の賃料相場を調査し、その範囲内で家賃を設定する。不動産鑑定士による評価書や、複数の不動産会社から取り寄せた査定書があれば、より強力な根拠となります。
常に「もしこの取引相手が全くの第三者だったら、同じ条件で契約するか?」という視点で、取引価格の客観的な妥当性を確保することが重要です。
経費の明確な按分ルール
事務所の家賃や水道光熱費、通信費、車両費など、法人と個人事業で共通して使用する経費がある場合、その費用をどのように分けるか(按分するか)が重要になります。
按分基準が曖昧だったり、恣意的だったりすると、経費の二重計上や不当な経費付け替えを疑われます。
経費を按分する際は、誰が見ても納得できる合理的で客観的な基準を設定し、その基準に基づいて計算した根拠資料を必ず保管しておく必要があります。
以下に、主な経費の合理的な按分基準の例を挙げます。
| 経費項目 | 合理的な按分基準の例 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| 事務所家賃 | 事業ごとの使用面積の割合 | 図面などで各事業が占有するスペースを明確にしておくと良い。 |
| 水道光熱費 | 使用時間、従業員数、コンセントの数などの割合 | 実態に即した基準を選ぶことが重要。メーターを分けるのが最も明確。 |
| 通信費 | 事業ごとの使用頻度や時間、回線契約の割合 | 業務日報や通話記録などで使用状況を記録しておく。事業ごとに回線を契約するのが理想。 |
| 車両費 | 事業ごとの走行距離や使用日数の割合 | 運転日報を作成し、いつ、どの事業のために、何キロ走行したかを記録する。 |
税務調査で質問された際に、設定した按分基準とその計算過程を明確に説明できるように準備しておくことが、リスクを回避する上で不可欠です。
消費税の納税義務に関する注意点
法人成りで個人事業を残す大きなメリットとして「消費税の免税期間の活用」が挙げられます。
原則として、資本金1,000万円未満の新設法人は設立から最大2年間、個人事業も課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税が免除されます。
しかし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始により、このメリットを単純に享受できなくなっている点に最大限の注意が必要です。
問題となるのは、法人と個人事業の間で取引がある場合です。
例えば、法人が課税事業者で、個人事業が免税事業者のままだとします。
この場合、個人事業は法人に対してインボイス(適格請求書)を発行できません。
インボイスを発行できないと、支払い側である法人は、個人事業に支払った費用にかかる消費税分を、自社が納める消費税額から差し引くこと(仕入税額控除)ができません。
つまり、法人の納税負担が増えてしまうのです。
このデメリットを回避するためには、個人事業側も「適格請求書発行事業者」として登録し、課税事業者になる必要があります。
しかし、そうすると個人事業としての消費税免除のメリットは失われます。
したがって、以下の点を総合的に検討し、個人事業を免税事業者のままにするか、課税事業者になるかを選択する必要があります。
- 法人と個人事業の間で、どの程度の規模の取引が発生するのか
- 個人事業の取引先は、法人(自分)以外にいるのか、その取引先はインボイスを必要としているか
- 消費税の免税メリット額と、法人が仕入税額控除できないことによる納税負担増加額のどちらが大きいか
安易に「免税事業者でいられるからお得」と判断するのではなく、インボイス制度の影響を踏まえた上で、法人と個人事業を合わせたグループ全体で最も有利になる選択肢は何かを慎重にシミュレーションすることが極めて重要です。
【社会保険編】保険料の負担はどう変わる?加入のルールを解説
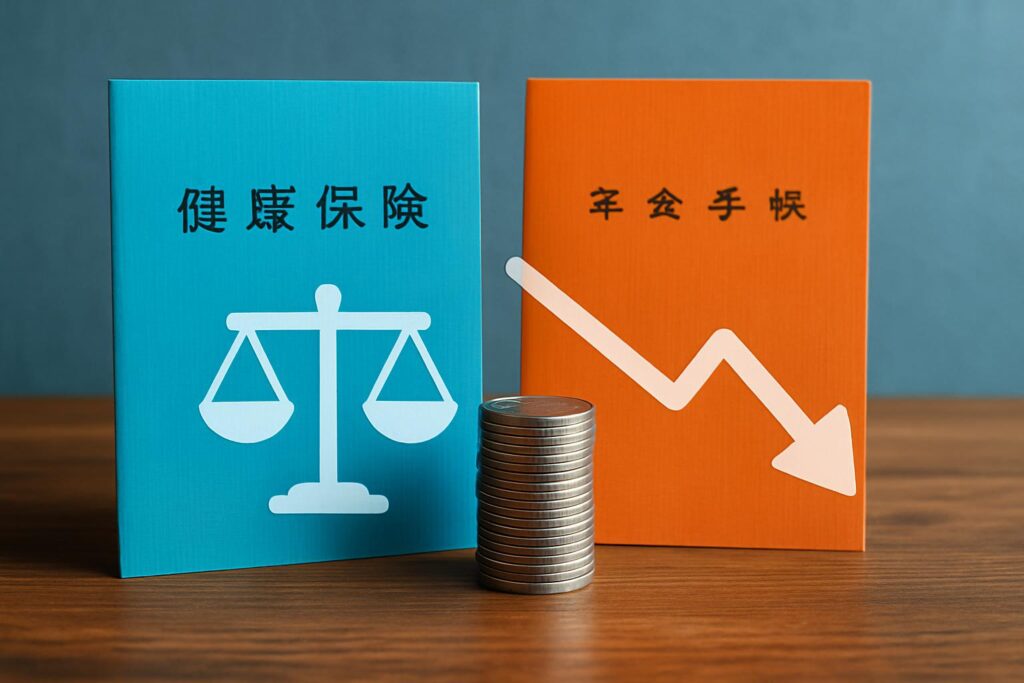
法人成りをして個人事業も残す場合、税金と並んで複雑になるのが社会保険の扱いです。
個人事業主時代の国民健康保険・国民年金から、法人の健康保険・厚生年金保険へ切り替わるのが基本ですが、二つの事業を並行することで「自分はどの保険に、どのように加入すれば良いのか?」と混乱しがちです。
ここでは、社会保険の基本的なルールから、二刀流ならではの特殊な加入パターン、そして保険料の決まり方までを詳しく解説します。
法人では社会保険への加入が義務
まず大原則として、法人を設立した場合、社会保険への加入は法律で義務付けられています。
たとえ社長一人の会社であっても、役員報酬を少しでも受け取っていれば加入しなければなりません。
ここでいう社会保険とは、主に「健康保険」と「厚生年金保険」を指します。
個人事業主時代の国民健康保険や国民年金との最も大きな違いは、保険料の負担割合です。
法人の社会保険料は、会社と役員(または従業員)が半分ずつ負担する「労使折半」となります。
給与や役員報酬から天引きされる保険料と同額を、会社も負担して納付する仕組みです。
保険料は高くなる傾向にありますが、その分、保障内容が手厚くなるメリットもあります。
例えば、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増えたり、健康保険には業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給される「傷病手当金」や、出産時に支給される「出産手当金」といった制度があったりします。
| 法人(役員・従業員) | 個人事業主 | |
|---|---|---|
| 医療保険 | 健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) | 国民健康保険 |
| 年金保険 | 厚生年金保険 | 国民年金 |
| 加入義務 | 原則、強制加入(常時1人以上使用する事業所) | 強制加入 |
| 保険料負担 | 会社と本人で折半(労使折半) | 全額自己負担 |
| 扶養の概念 | あり(被扶養者の保険料負担なし) | なし(家族の人数に応じて保険料が増加) |
個人事業としての社会保険の扱い
一方、個人事業主が加入するのは、原則として市区町村が運営する「国民健康保険」と「国民年金」です。
こちらは保険料が全額自己負担となります。
国民健康保険料は前年の所得などに応じて決まり、国民年金保険料は所得にかかわらず一律です(免除・猶予制度あり)。
法人成りをして個人事業を残す場合、個人事業主として加入していた国民健康保険・国民年金からは脱退し、法人の社会保険に切り替えるのが基本的な流れとなります。
法人成りで個人事業を残す場合の社会保険加入パターン
それでは、法人と個人事業を両立する場合、具体的に社会保険はどのようになるのでしょうか。
重要なポイントは、主たる勤務先である法人で社会保険に加入するという点です。
そして、法人から役員報酬を受け取り、かつ個人事業からも事業所得がある場合、両方の所得を合算して社会保険料を決定する必要があります。
この手続きのために、日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出しなければなりません。
この届出を行うことで、法人での役員報酬(標準報酬月額)と個人事業での報酬(標準賞与額として年に1回申告)を合算した金額を基に社会保険料が計算されます。
そして、算出された保険料を、それぞれの報酬額の比率に応じて按分し、法人と個人事業所(※)からそれぞれ納付することになります。
※個人事業が社会保険の適用事業所でない場合、保険料はすべて法人が納付し、個人負担分は役員報酬から天引きされます。
具体的なパターンを見ていきましょう。
| 状況 | 加入する社会保険 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 法人から役員報酬があり、個人事業の所得もある | 法人の健康保険・厚生年金に加入 | 「二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出。両方の報酬を合算して保険料を計算・納付。 |
| 法人からは役員報酬ゼロで、個人事業の所得のみ | 個人事業主として国民健康保険・国民年金に加入 | 法人の社会保険には加入できない。個人事業主としての加入義務を継続する。 |
| 法人の社会保険に加入し、家族を扶養に入れる | 法人の健康保険・厚生年金に加入 | 被扶養者(異動)届を提出。被扶養者の収入等が一定の条件を満たせば、扶養に入れることができる。 |
このように、法人成りで個人事業を残す場合、社会保険の扱いは「どこから主な報酬を得ているか」によって決まります。
特に複数の事業所から報酬を得る場合は「二以上事業所勤務届」の提出が必須となるため、忘れないように注意が必要です。
手続きが複雑で分かりにくい場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
法人成り後も個人事業を残すことは可能で、所得分散による節税や消費税の免税など多くのメリットがあります。
しかし、経理事務の負担が増え、税務調査で所得移転を疑われるリスクも伴います。
最も重要な結論は、法人と個人の事業内容やお金の流れを明確に区分し、取引の客観性を担保することです。
メリットを最大限に活かすため、事前に税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。