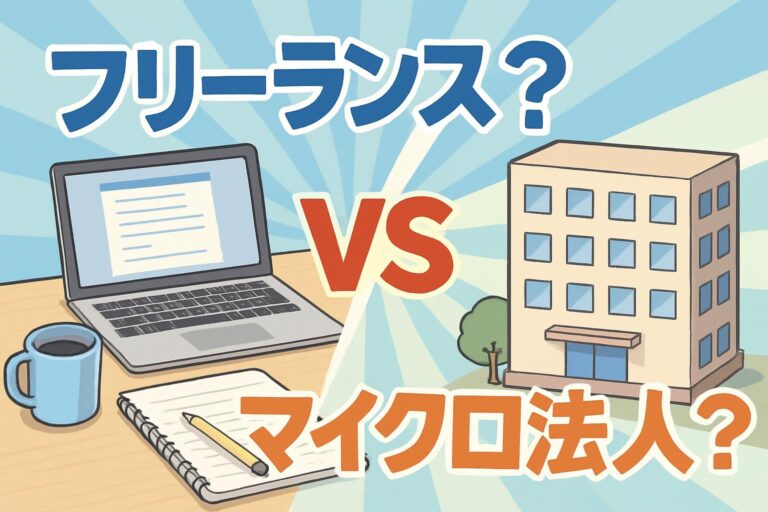フリーランスとして順調に売上を伸ばしているものの、「思ったより手取りが増えない」「国民健康保険料や国民年金が高すぎる」といった悩みを抱えていませんか?
その悩み、もしかしたら「マイクロ法人」の設立で解決できるかもしれません。
この記事では、フリーランスがマイクロ法人を設立するべきか判断するために、年収500万円、800万円、1000万円といった具体的なシミュレーションを用いて、どちらが得になるのかを徹底比較します。
結論を先に述べると、事業所得が600万円を超えたあたりからマイクロ法人の節税効果は大きくなり、特に年収800万円以上の方であれば、社会保険料を年間数十万円単位で削減し、手取り額を大幅に増やせる可能性が高いです。
本記事を読めば、マイクロ法人で社会保険料を劇的に下げる仕組みから、設立のメリット・デメリット、株式会社と合同会社どちらを選ぶべきか、最適な役員報酬の設定額まで、あなたの疑問がすべて解決します。
フリーランスのままでいるべきか、マイクロ法人を設立すべきか、最適な選択をするための判断材料としてぜひお役立てください。
フリーランスの悩み「高い税金と社会保険料」はマイクロ法人で解決できる
フリーランスとして独立し、順調に売上が伸びてきたものの、「思ったより手元にお金が残らない…」と感じていませんか?
その大きな原因は、
所得の増加に比例して重くのしかかる「税金」と「社会保険料」です。
特に、国民健康保険料は所得に応じて上限近くまで上がり続けるため、多くのフリーランスにとって悩みの種となっています。
会社員時代は給与から天引きされていたため意識しづらかったこれらの負担が、確定申告を経て納税通知書が届いたときに、その金額の大きさに愕然とした経験がある方も少なくないでしょう。
しかし、この根深い悩みを解決し、賢く手取りを増やすための強力な選択肢があります。
それが「マイクロ法人」の設立です。
この章では、まずフリーランスがなぜ手取りが少ないと感じるのか、その構造的な問題を解き明かし、次にマイクロ法人を活用することで、特に社会保険料の負担を劇的に軽減できる仕組みについて、分かりやすく解説していきます。
なぜフリーランスは手取りが少ないと感じるのか
フリーランス(個人事業主)の手取りが伸び悩む最大の理由は、会社員とは異なる税金と社会保険料の仕組みにあります。
売上がそのまま収入になるわけではなく、そこから経費を差し引いた「所得」に対して、様々な税金や社会保険料が課せられるのです。
フリーランスと会社員の負担構造の違い
具体的にどのような違いがあるのか、会社員と比較してみましょう。
| 項目 | フリーランス(個人事業主) | 会社員 |
|---|---|---|
| 所得税・住民税 | 事業所得全体に対して課税される(累進課税)。 | 給与所得に対して課税される。給与所得控除がある。 |
| 健康保険 | 国民健康保険に加入。所得に応じて保険料が増加し、上限額も高い。扶養の概念がなく、家族の分も負担が増える。 | 健康保険(協会けんぽ等)に加入。保険料は標準報酬月額で決まり、会社と折半で負担する。扶養家族の保険料はかからない。 |
| 年金 | 国民年金に加入。保険料は定額。 | 厚生年金に加入。保険料は標準報酬月額で決まり、会社と折半で負担する。将来の受給額も手厚い。 |
| その他 | 所得290万円超で個人事業税(一部業種)、売上1,000万円超で消費税の納税義務が発生する。 | 基本的に給与から天引きされるため、追加の税負担は少ない。 |
この表で特に注目すべきは「健康保険」と「年金」です。会社員は社会保険料を会社が半分負担してくれますが、フリーランスは全額自己負担です。
さらに、国民健康保険料は所得が増えれば増えるほど高額になり、年間100万円を超えるケースも珍しくありません。
この社会保険料の負担の大きさが、フリーランスの手取りを圧迫する最大の要因となっているのです。
マイクロ法人で社会保険料を劇的に下げる仕組みとは
マイクロ法人を設立する最大のメリットは、この高額になりがちな社会保険料を合法的にコントロールし、最適化できる点にあります。
その鍵となるのが、「個人事業主」と「法人(自分自身が社長)」の二刀流という働き方です。
仕組みは非常にシンプルです。
- フリーランスとしての「個人事業」はそのまま継続する。
- 自分ひとりが役員(社長)の「マイクロ法人」を設立する。
- 法人を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられる。
- 法人から自分自身へ支払う「役員報酬」を、社会保険料が最も安くなる金額(例:月額45,000円など)に設定する。
- 事業の売上の大部分は、引き続き「個人事業」で受け取る。
この仕組みにより、これまで個人事業の所得全体にかかっていた国民健康保険料が、マイクロ法人から受け取る低い役員報酬を基準とした社会保険料に切り替わります。
これにより、社会保険料の負担を劇的に下げることが可能になるのです。
フリーランスのままの場合とマイクロ法人設立後の比較
| 比較項目 | フリーランスのままの場合 | マイクロ法人+個人事業主の場合 |
|---|---|---|
| 収入の受け取り方 | すべての売上を個人事業の収入とする。 | 一部を法人の役員報酬、大部分を個人事業の収入とする。 |
| 加入する社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金(法人で加入) |
| 社会保険料の計算基礎 | 個人事業の所得全体(経費を引いた後の利益) | 法人から受け取る低い役員報酬額のみ |
| 結果 | 所得が増えるほど社会保険料が青天井に高くなる。 | 個人事業でいくら稼いでも、法人の社会保険料は低いまま維持できる。 |
例えば、個人事業の所得が800万円ある場合、国民健康保険料は上限に近い金額になります。
しかし、マイクロ法人を設立し役員報酬を月額5万円に設定すれば、社会保険料(健康保険・厚生年金)は月々15,000円程度に抑えられます。
年間で数十万円から、場合によっては100万円以上の社会保険料を削減できるインパクトがあるのです。
さらに、厚生年金に加入することで、国民年金のみの場合に比べて将来受け取れる年金額(老齢厚生年金)が増えるという、将来への安心につながるメリットも享受できます。
【シミュレーション】年収いくらからマイクロ法人は得になる?

「マイクロ法人を設立すると手取りが増える」という話はよく聞きますが、具体的に自分の年収だとどれくらい得になるのか、あるいは逆に損をしてしまうのか、イメージが湧きにくい方も多いでしょう。
ここでは、具体的な年収を例に挙げ、フリーランス(個人事業主)のままでいる場合とマイクロ法人を設立した場合の手取り額を徹底比較します。
シミュレーションにあたり、以下の共通条件を設定します。
ご自身の状況と照らし合わせながらご覧ください。
- 対象者: 東京23区在住、40歳未満、独身(扶養家族なし)のフリーランス
- 事業形態: 青色申告を行う個人事業主
- 経費: 売上(年収)の30%と仮定
- マイクロ法人設定:
- 役員報酬:月額6万円(年額72万円)※社会保険料が最適化されやすい金額
- 法人利益:売上から経費と役員報酬を差し引いた額
- 法人維持費:法人住民税均等割(7万円)+税理士費用(年間24万円)=年間31万円
※本シミュレーションは概算です。所得控除は基礎控除、青色申告特別控除(65万円)、社会保険料控除のみを考慮しており、実際の税額や社会保険料は個々の状況により変動します。
年収500万円ではフリーランスに軍配
まず、多くのフリーランスが目標とする年収500万円のケースを見てみましょう。
この段階では、マイクロ法人化は必ずしも得策とは言えません。
| 項目 | フリーランス(個人事業主) | マイクロ法人+個人事業主 |
|---|---|---|
| 売上(年収) | 500万円 | 500万円 |
| 経費 | 150万円 | 150万円 |
| 所得(利益) | 350万円 | 【法人】247万円 【個人】72万円(役員報酬) |
| 税金(所得税・住民税・法人税等) | 約48万円 | 約46万円 |
| 社会保険料(国保・年金/健保・厚年) | 約60万円 | 約29万円 |
| 法人維持費 | 0円 | 31万円 |
| 最終的な手取り額(概算) | 約242万円 | 約216万円 |
シミュレーションの結果、年収500万円の段階では、フリーランスのままの方が手取り額が多くなることがわかります。
マイクロ法人は社会保険料を約31万円も削減できますが、それを上回る法人維持費(31万円)と、フリーランスの強みである青色申告特別控除(最大65万円)が使えなくなる影響が大きいためです。
(※個人の役員報酬部分では給与所得控除が適用されますが、青色申告特別控除ほどのインパクトはありません)
法人設立・維持コストが、節税や社会保険料削減のメリットを上回ってしまうため、この年収帯での法人化は慎重に検討すべきでしょう。
年収800万円から1000万円でマイクロ法人の効果が最大化
次に、事業が軌道に乗り、年収が800万円を超えてきたケースをシミュレーションしてみましょう。
この価格帯から、マイクロ法人の真価が発揮され始めます。
| 項目 | フリーランス(個人事業主) | マイクロ法人+個人事業主 |
|---|---|---|
| 売上(年収) | 800万円 | 800万円 |
| 経費 | 240万円 | 240万円 |
| 所得(利益) | 560万円 | 【法人】457万円 【個人】72万円(役員報酬) |
| 税金(所得税・住民税・法人税等) | 約121万円 | 約100万円 |
| 社会保険料(国保・年金/健保・厚年) | 約98万円 | 約29万円 |
| 法人維持費 | 0円 | 31万円 |
| 最終的な手取り額(概算) | 約341万円 | 約400万円 |
年収800万円のケースでは、マイクロ法人を設立した方が、手取り額が年間約59万円も多くなるという結果になりました。
この差が生まれる最大の要因は、やはり社会保険料です。フリーランスの国民健康保険料は所得に応じて上限なく上がっていきますが、マイクロ法人では役員報酬を低く抑えることで、健康保険・厚生年金保険料を最小限にできます。
この社会保険料の削減効果が、法人維持コストを大きく上回るのです。
さらに年収1000万円になると、その効果はさらに拡大します。
| 項目 | フリーランス(個人事業主) | マイクロ法人+個人事業主 |
|---|---|---|
| 売上(年収) | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 経費 | 300万円 | 300万円 |
| 所得(利益) | 700万円 | 【法人】597万円 【個人】72万円(役員報酬) |
| 税金(所得税・住民税・法人税等) | 約172万円 | 約132万円 |
| 社会保険料(国保・年金/健保・厚年) | 約117万円 | 約29万円 |
| 法人維持費 | 0円 | 31万円 |
| 最終的な手取り額(概算) | 約411万円 | 約508万円 |
年収1000万円では、その差は年間約97万円にまで広がります。
所得税・住民税の累進課税による負担増が大きくなるこの年収帯では、所得を個人の役員報酬と法人利益に分散できるマイクロ法人の税制上のメリットも大きく寄与します。
所得(利益)ベースで考える法人化の損益分岐点
ここまで「年収(売上)」を基準に見てきましたが、より正確な判断をするためには「所得(利益)」ベースで考えることが重要です。
なぜなら、Webライターのように経費が少ない職種と、仕入れや設備投資が多い物販・製造業では、同じ年収でも所得が大きく異なるからです。
一般的に、マイクロ法人化を検討すべき損益分岐点は、フリーランスとしての事業所得(売上から経費を引いた額)が500万円〜700万円を超えたあたりと言われています。
この水準を超えると、社会保険料の負担が急増し、所得税率も上がるため、マイクロ法人による節税・社会保険料削減効果が法人維持コストを上回りやすくなります。
ただし、この損益分岐点はあくまで一般的な目安です。以下の要素によって、最適なタイミングは一人ひとり異なります。
- 扶養家族の有無: 扶養家族がいる場合、社会保険の扶養制度を利用できるマイクロ法人のメリットはさらに大きくなります。
- お住まいの自治体: 国民健康保険料は自治体によって計算方法や料率が異なるため、お住まいの地域によって損益分岐点は変動します。
- 許容できる手間とコスト: 法人設立の手続きや毎年の決算申告、税理士費用といった手間とコストを許容できるかという、個人の価値観も重要な判断材料です。
最終的な判断を下す前には、ご自身の具体的な売上や経費、家族構成などの情報をもとに、税理士などの専門家に相談し、詳細なシミュレーションを依頼することをおすすめします。
フリーランスとマイクロ法人のメリット・デメリットを完全比較

マイクロ法人化を検討する上で、そのメリットとデメリットを正確に理解することは不可欠です。
フリーランス(個人事業主)のままでいることの利点も含め、それぞれの働き方が持つ特徴を多角的に比較し、あなたにとって最適な選択肢を見つけるための判断材料を整理していきましょう。
マイクロ法人のメリット 節税・信用・経費
マイクロ法人の最大の魅力は、フリーランス時代には享受できなかった様々な恩恵を受けられる点にあります。
特に「節税」「社会的信用」「経費計上」の3つの側面で大きなメリットがあります。
節税効果:社会保険料と税金の最適化
マイクロ法人化による節税効果は、主に社会保険料の最適化と税制上の優遇措置から生まれます。
- 社会保険料の劇的な削減
フリーランスが加入する国民健康保険料は前年の所得に応じて決まるため、収入が増えるほど負担も大きくなります。一方、マイクロ法人を設立すると、役員として健康保険・厚生年金保険(社会保険)に加入します。この社会保険料は、会社から受け取る「役員報酬」の金額(標準報酬月額)に基づいて算出されます。そのため、役員報酬を意図的に低く設定することで、社会保険料の負担を大幅に軽減できるのです。個人事業の利益はそのまま法人にプールし、必要な生活費だけを役員報酬として受け取る、という戦略が可能になります。 - 給与所得控除の適用
役員報酬は「給与所得」として扱われるため、フリーランスの事業所得にはない「給与所得控除」が適用されます。これは、いわば給与所得者向けの「みなし経費」であり、収入に応じて一定額が課税所得から差し引かれるため、所得税・住民税の負担が軽くなります。 - 所得の分散による税率の抑制
個人事業の利益を法人に移し、自身への役員報酬と法人に残す利益に分散させることで、所得税の累進課税(所得が高いほど税率が上がる仕組み)を回避しやすくなります。所得が一定額を超えると、所得税率よりも法人税率の方が低くなるため、トータルでの税負担を抑えることができます。 - 消費税の免税事業者
原則として、資本金1,000万円未満の新設法人は、設立から最大2年間、消費税の納税が免除されます。(※インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者として登録した場合は初年度から課税事業者となります。)
社会的信用の向上
法人格を持つことで、個人事業主よりも高い社会的信用を得られる場面が多くなります。
- 取引の拡大
企業によっては「法人でなければ契約しない」という方針(与信管理)のところも少なくありません。法人化することで、これまで取引できなかった大企業との契約や、新しいビジネスチャンスが広がる可能性があります。 - 資金調達の有利化
金融機関からの融資審査において、法人は個人事業主よりも有利になる傾向があります。事業計画の透明性や会計の厳格さが評価され、より大きな金額の融資や、より良い条件での借入が期待できます。日本政策金融公庫の新創業融資制度なども活用しやすくなります。 - 採用活動の円滑化
将来的に従業員を雇用したいと考えた場合、「株式会社」や「合同会社」といった法人格がある方が、求職者に対して安心感を与え、採用活動をスムーズに進めやすくなります。
経費計上範囲の拡大
法人化すると、個人事業主では経費として認められにくい支出も、損金として計上できる範囲が広がります。
- 役員社宅(家賃補助)
個人名義で借りている住居を法人契約に切り替え、役員社宅として扱うことで、家賃の大部分を会社の経費にできます。役員は会社に一定の賃料を支払うだけで済むため、実質的な家賃負担を大幅に削減できます。 - 出張手当(日当)
出張旅費規程を整備すれば、出張の際に実費(交通費・宿泊費)とは別に、非課税の出張手当(日当)を役員に支給できます。この手当は会社の経費(損金)となり、受け取った役員個人の所得税・住民税はかかりません。 - 生命保険料
役員を被保険者とする生命保険に加入し、保険の種類によっては支払った保険料の全額または一部を会社の経費にすることができます。将来の退職金準備や万が一の保障を、節税しながら行えるというメリットがあります。 - 退職金の準備
将来、役員を退任する際に「役員退職慰労金」を支給できます。退職金は税制上非常に優遇されており、他の所得と分離して計算される「退職所得控除」が適用されるため、税負担を大きく抑えてまとまった資金を受け取ることが可能です。
マイクロ法人のデメリット コスト・手間・制約
多くのメリットがある一方で、マイクロ法人には個人事業主にはないデメリットも存在します。
特に「コスト」「手間」「制約」の3つの観点から、事前に把握しておくべき注意点を見ていきましょう。
| 分類 | 具体的な内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| コスト | 設立費用 | 株式会社で約25万円、合同会社でも約10万円程度の法定費用(登録免許税、定款認証手数料など)が必要です。 |
| 維持費用(法人住民税均等割) | 事業が赤字であっても、最低でも年間約7万円の法人住民税(均等割)を納付する義務があります。 | |
| 税理士費用 | 法人の決算申告は複雑なため、税理士への依頼がほぼ必須です。顧問料や決算料で年間20万円~40万円程度の費用が発生します。 | |
| 手間 | 設立手続き | 定款の作成・認証、登記申請など、個人事業主の開業届とは比較にならないほど手続きが煩雑で時間がかかります。 |
| 経理・税務処理 | 複式簿記による厳格な会計処理が義務付けられ、決算申告や税務調査への対応など、専門的な知識が求められます。 | |
| 社会保険手続き | 役員報酬の決定、社会保険の加入・変更手続き、年末調整など、個人事業主にはなかった労務関連の事務作業が発生します。 | |
| 制約 | 資金の自由度 | 会社の資産と個人の資産は明確に区別されます。事業で得た利益を、役員報酬や配当といった正規の手続き以外で自由に引き出すことはできません。 |
| 廃業手続き | 事業をやめる際も、解散登記や清算結了登記といった法的な手続きが必要で、時間と費用(司法書士費用など)がかかります。 |
個人事業主(フリーランス)のままでいるメリット
マイクロ法人化の検討にあたり、現状のフリーランス(個人事業主)の働き方が持つメリットを再確認することも重要です。
場合によっては、法人化せずにフリーランスを続ける方が合理的なケースもあります。
手軽さと自由度の高さ
個人事業主の最大の魅力は、そのシンプルさと自由度の高さにあります。
- 開業・廃業の手軽さ
税務署に開業届を一枚提出するだけで、すぐに事業を始められます。特別な設立費用はかかりません。同様に、事業をやめる際も廃業届を提出するだけで済み、法人ような複雑な清算手続きは不要です。 - 会計処理の簡便さ
会計処理は法人に比べてシンプルです。会計ソフトを使えば、青色申告(65万円控除)の要件を満たす帳簿作成も比較的容易に行え、税理士に依頼せず自分で確定申告を完結させることも十分可能です。 - 資金の自由度
事業で得た利益はすべて個人のものであり、事業用資金と生活費の区別が緩やかです。必要な時に必要なだけ、事業用の口座から資金を自由に引き出して使うことができます。
コストの低さ
事業運営にかかる固定コストを最小限に抑えられるのも、個人事業主の大きな利点です。
- 設立・維持コストがゼロ
法人設立費用はもちろん、赤字の場合に課される法人住民税均等割のような固定的な税金もありません。利益が出なければ所得税・住民税はかからず、コストを抑えて事業を継続できます。 - 各種控除制度の活用
青色申告特別控除(最大65万円)や、個人事業主のための退職金制度である小規模企業共済(掛金が全額所得控除)など、フリーランス向けに用意された節税制度を有効活用できます。
これらのメリットから、事業規模がまだ小さい、所得の変動が大きい、あるいは事務手続きの煩雑さを避けたいといった場合には、個人事業主のままでいることが最適な選択となるでしょう。
マイクロ法人設立に向いているフリーランスの職種と特徴

マイクロ法人を設立すれば、誰もが必ず得をするわけではありません。
ご自身の年収(所得)、事業内容、そして将来のキャリアプランによって、その効果は大きく変わります。
この章では、シミュレーション結果を踏まえ、どのようなフリーランスがマイクロ法人設立に向いているのか、具体的な職種や特徴を深掘りしていきます。
ご自身が当てはまるか、じっくりと確認してみてください。
マイクロ法人化を強くおすすめする人の条件
マイクロ法人設立のメリットを最大限に享受できるのは、特定の条件を満たしたフリーランスです。
特に、社会保険料の負担を重く感じており、安定した事業基盤を持つ方は、法人化による手取りアップの効果を実感しやすいでしょう。
以下に挙げる条件に複数当てはまる方は、マイクロ法人設立を積極的に検討する価値があります。
| カテゴリ | 具体的な条件 | 理由 |
|---|---|---|
| 所得(利益) | 個人事業の所得が継続的に800万円を超えている | 所得税・住民税・国民健康保険料の負担が非常に大きくなるライン。法人化による社会保険料削減メリットが、法人設立・維持コストを上回り始めます。 |
| 事業の安定性 | 毎月安定した収益が見込める | マイクロ法人では役員報酬を毎月定額で支払うため、収入の変動が少ない事業モデルの方が資金繰りのリスクを抑えられます。 |
| 職種 | 利益率が極めて高い職種(ITエンジニア、Webデザイナー、コンサルタント、Webライター、動画編集者など) | 仕入れや大きな設備投資が不要で、売上の大半が利益になる職種は、法人に移す利益のコントロールがしやすく、節税効果を最大化できます。 |
| 将来の展望 | 事業拡大やBtoB取引の強化を考えている | 法人格を持つことで社会的信用度が向上し、金融機関からの融資や大手企業との取引が有利になる場合があります。 |
| プライベート | 扶養している家族がいる | 自分一人の保険料で配偶者や子供を扶養に入れられるため、家族全員分の国民健康保険料を支払う場合に比べて大幅な負担減になります。 |
| マインド | 税金や社会保険に関する知識欲があり、事務手続きを厭わない | 法人設立や決算、社会保険の手続きなど、個人事業主時代にはなかったタスクが発生します。これらに前向きに取り組めるか、専門家に外注するコストを許容できるかが重要です。 |
フリーランスのままが良い人の条件
一方で、すべてのフリーランスにマイクロ法人化がおすすめできるわけではありません。
状況によっては、法人化することでかえってコスト増や手間がかかり、デメリットが上回ってしまうケースもあります。
以下の条件に当てはまる方は、現時点では無理に法人化せず、個人事業主のまま活動を続ける方が賢明かもしれません。
| カテゴリ | 具体的な条件 | 理由 |
|---|---|---|
| 所得(利益) | 個人事業の所得が500万円以下である | この所得水準では、法人化による社会保険料削減メリットよりも、法人住民税の均等割(最低でも年間7万円)や税理士費用などの維持コストの方が高くなる可能性が高いです。 |
| 事業の安定性 | 年によって収入の変動が激しい、または単発の仕事が中心 | 収入が不安定な場合、固定の役員報酬を支払い続けることが経営上のリスクになります。収入が途絶えても役員報酬の支払いは発生し、社会保険料の負担も続きます。 |
| 事業内容 | 飲食業や小売業など、仕入れや店舗運営コストが大きい事業 | 利益率が低い事業モデルの場合、個人事業と法人で利益を分散させるマイクロ法人のスキームを組みにくく、節税効果が限定的になります。 |
| マインド | 事務作業や手続きが極端に苦手で、できるだけ本業に集中したい | 法人設立・運営には複雑な手続きが伴います。これらの管理が大きなストレスになる、または外注コストをかけたくない場合は、シンプルな個人事業主の方が適しています。 |
| 節税制度の活用 | 小規模企業共済やiDeCoを満額利用しており、現状の節税に満足している | 個人事業主向けの節税制度を最大限活用することで、法人化せずとも所得を十分に圧縮できている場合は、急いで法人化する必要性は低いでしょう。 |
最終的な判断は、目先の節税額だけでなく、ご自身の事業の将来性やライフプラン、そして「経営者」としての視点を持てるかどうかも含めて総合的に行うことが重要です。
失敗しないマイクロ法人設立のためのQ&A

マイクロ法人という選択肢に魅力を感じても、設立や運営に関する具体的な疑問や不安は尽きないものです。
いざ行動に移してから「こんなはずではなかった」と後悔しないために、フリーランスが抱きがちな疑問についてQ&A形式で詳しく解説します。
株式会社と合同会社どっちがいい?
結論から言うと、フリーランスが設立するマイクロ法人であれば、設立費用が安く、運営の手間も少ない「合同会社」が圧倒的におすすめです。
株式会社の社会的信用の高さを魅力に感じる方もいますが、1人社長で外部からの出資を想定しないマイクロ法人では、そのメリットは限定的です。
両者の違いを以下の表で比較してみましょう。
| 項目 | 合同会社(LLC) | 株式会社(KK) |
|---|---|---|
| 設立費用(法定費用) | 約6万円~ | 約20万円~ |
| 役員の任期 | なし(定款で定めることも可能) | 原則2年(最長10年まで伸長可) |
| 役員変更登記 | 任期がないため原則不要 | 任期満了ごとに必要(費用発生) |
| 決算公告の義務 | なし | あり(官報掲載などで費用発生) |
| 意思決定の仕組み | 社員(出資者)の同意 | 株主総会での決議 |
| 社会的信用度 | 株式会社に比べるとやや低い | 高い |
このように、コストと手間の両面で合同会社に優位性があります。
マイクロ法人の目的はあくまで「社会保険料の最適化」であり、事業の器はできるだけシンプルで低コストなものが望ましいです。
将来的に事業を拡大し、外部からの資金調達や上場を目指す段階になった際に、株式会社へ組織変更(株式会社化)することも可能です。
役員報酬はいくらに設定すべき?
役員報酬の金額設定は、マイクロ法人スキームの肝となる最も重要なポイントです。
基本戦略は、社会保険料の負担が最も少なくなる金額に設定することです。
健康保険・厚生年金保険の保険料は「標準報酬月額」という区分で決まります。
この等級が最も低い「1等級」になるように役員報酬を設定します。
例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の場合、標準報酬月額の最低額は健康保険が58,000円、厚生年金が88,000円です。
両者を合わせた社会保険料を最小にするには、月額の役員報酬を63,000円未満(例えば45,000円や50,000円)に設定するのが一般的です。
ただし、いくつか注意点があります。
- 定期同額給与の原則
役員報酬は、事業年度の開始から3ヶ月以内に決定する必要があり、その後は原則として事業年度の終了まで金額を変更できません。これを「定期同額給与」と呼びます。恣意的な利益調整を防ぐためのルールであり、自由に報酬額を変えられないことを覚えておきましょう。 - 地域の保険料率を確認
健康保険料率は、加入する健康保険組合(多くは協会けんぽ)の都道府県支部によって異なります。設立前に必ずご自身の地域の最新の保険料額表を確認してください。 - 生活費の捻出方法
月額数万円の役員報酬だけでは生活できません。生活費は、あくまで個人事業主としての事業で得た利益から賄います。マイクロ法人の役員報酬は、社会保険に安く加入するためのものと割り切って考えましょう。
個人事業とマイクロ法人の二刀流は可能?
はい、可能です。というより、この「二刀流」こそがマイクロ法人スキームの基本形です。
フリーランスとしての活動は個人事業主として継続し、それとは別にマイクロ法人を設立して、その法人の役員として社会保険に加入します。
このスキームを税務上も正しく運用するためには、非常に重要な注意点があります。
それは、個人事業とマイクロ法人の事業内容を明確に分けることです。
もし両者の事業内容が全く同じだと、税務署から「実態は一つの事業なのに、税金や社会保険料を安くするためだけに法人を設立した」と判断され、租税回避行為とみなされるリスクがあります。
そうなると、法人の存在が否認され、追徴課税を課される可能性もゼロではありません。
事業内容を適切に分けるための具体例をいくつか紹介します。
- Webライターの場合
- 個人事業:記事執筆、コンテンツ制作
- マイクロ法人:Webサイト管理、SEOコンサルティング、クライアントへの請求管理業務
- Webデザイナーの場合
- 個人事業:デザイン制作、コーディング
- マイクロ法人:デザイン関連のコンサルティング、プロジェクト管理、自身のポートフォリオサイトの運営・管理
- ITエンジニアの場合
- 個人事業:プログラミング、システム開発
- マイクロ法人:技術コンサルティング、IT関連研修の講師、自社サービスの開発・運営
このように、主たる業務を個人事業で、管理業務やコンサルティング、周辺業務などを法人で請け負う形が一般的です。
そして、個人事業から法人へ、法人が行う業務に対する「業務委託費」を支払うことで、法人側に売上を計上し、事業の実態を作ります。
インボイス制度導入による影響は?
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、マイクロ法人スキームにも影響を与えます。
結論として、消費税の負担は増える可能性がありますが、スキーム自体のメリットがなくなるわけではありません。
影響は「個人事業」と「マイクロ法人」の両面で考える必要があります。
個人事業主としての影響
取引先(クライアント)が課税事業者である場合、インボイス(適格請求書)を発行できないと、取引先は仕入税額控除が受けられず、税負担が増えてしまいます。
そのため、取引の継続や新規契約において不利になる可能性があり、多くのフリーランスは個人事業として「適格請求書発行事業者」に登録する必要が出てきます。
これにより、これまで免税事業者だった方も消費税の納税義務が発生します。
マイクロ法人としての影響
前述の通り、マイクロ法人は個人事業から業務委託費を受け取ることで売上を立てます。
このとき、個人事業主(あなた自身)が課税事業者として消費税を納めている場合、法人への支払いを仕入税額控除の対象にするためには、マイクロ法人側も適格請求書発行事業者となり、個人事業主宛にインボイスを発行する必要があります。
結果として、マイクロ法人側でも消費税の納税義務が発生します。
つまり、インボイス制度に対応すると、個人と法人の両方で消費税を納税するケースが多くなります。しかし、マイクロ法人の売上(役員報酬の原資+α)は少額に抑えるため、法人側の消費税負担は限定的です。
簡易課税制度を選択すれば、事務負担も軽減できます。
インボイス制度による消費税の負担増を考慮しても、それを上回る社会保険料の削減メリットが得られるのであれば、マイクロ法人を設立する価値は依然として高いと言えるでしょう。
まとめ
本記事では、フリーランスが直面する税金や社会保険料の負担を軽減する選択肢として、マイクロ法人設立の有効性をシミュレーションを交えて徹底比較しました。
結論として、フリーランスの事業所得が800万円を超えるあたりから、マイクロ法人を設立することで社会保険料が劇的に削減され、手取り額を最大化できる可能性が高まります。
これは、役員報酬を社会保険料が最低限になる金額に設定し、残りの利益を個人事業の所得として受け取る「二刀流」によって実現されます。
一方で、マイクロ法人には設立費用や維持コスト、そして煩雑な事務手続きといったデメリットも存在します。
そのため、所得が500万円以下の場合や、事業が不安定な段階では、コスト倒れになるリスクもあり、個人事業主のままの方が有利と言えるでしょう。
ご自身の年収や事業の安定性、そして将来の展望を踏まえ、マイクロ法人化が本当に最適な選択肢なのかを見極めることが重要です。
最終的な判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせたアドバイスを受けることを強くおすすめします。