マイクロ法人とは何か
マイクロ法人の定義と特徴
マイクロ法人とは、従業員の数が極めて少なく、ほとんどの場合は一人または家族だけで運営される非常に小規模な株式会社や合同会社を指します。
法律上の特別な定義があるわけではありませんが、「役員のみ」で構成されており、正社員やパート・アルバイトといった従業員がいない法人を一般的に指します。
主に節税を目的として設立されるケースや、個人事業主が事業形態の切り替え先として活用するケースが増えています。
| 特徴 | 概要 |
|---|---|
| 規模 | 資本金は数十万円〜100万円程度、役員1〜2名で運営 |
| 人員 | 役員のみで従業員は基本的にいない |
| 設立形態 | 株式会社または合同会社が一般的 |
| 利用目的 | 節税、社会保険加入、副業・二拠点経営、事業の分散など |
| 税務申告 | 個人事業主よりも複雑だが、経費計上の幅が広がる |
自分自身しか働いていない法人となるため、社内での意思決定スピードが速く、運営コストも低く抑えられるという利点があります。
一方で、規模が小さいため社会的信用や資金調達力には課題が残る場合もあります。
設立の背景と増加の理由
近年、マイクロ法人は起業家、フリーランス、個人事業主の間で注目を集めています。
その背景には、以下のような社会・経済的要因が影響しています。
| 背景/理由 | 詳細 |
|---|---|
| 節税対策 | 所得分散や法人税率の活用により、個人事業主よりも税負担を軽減できる場合が多い |
| 社会保険(厚生年金など)のメリット | 法人化によって社会保険に加入でき、将来の年金受給額や保障を強化できる |
| 副業・二拠点運営の需要 | 本業に加えて複数の収入源を持つ目的や、複数拠点での事業展開に適している |
| 低コストで設立可能 | 登記や設立の費用が低く、初期投資のリスクが小さい |
| 働き方改革の推進 | 多様な働き方が認められる現代社会で、個人の自己実現や副業解禁の流れともマッチ |
これらの理由から、マイクロ法人はサラリーマンやフリーランス、個人事業主から幅広く支持を集めており、設立件数も年々増加傾向にあります。
特に、社会保険や法人税制を上手に活用したいというニーズが、マイクロ法人増加の大きな要因の一つです。
マイクロ法人にかかる主な税金

法人税の基本的な仕組み
マイクロ法人にも通常の株式会社と同様に法人税が課されます。
法人税は、会社の年度ごとの所得金額(利益)に対してかかる国税です。
法人の利益に応じて税率が異なり、資本金1億円以下の中小企業には軽減税率が適用される仕組みとなっています。
マイクロ法人として運営する場合、ほとんどのケースでこの中小企業の枠に該当します。
法人税の納付は事業年度終了後、定められた期間内(原則として2か月以内)に申告・納税する必要があります。
また、法人税には「予定納税」と呼ばれる前払い制度が設けられている点も押さえておきましょう。
法人住民税や事業税などその他の税目
マイクロ法人を設立すると、法人税以外にもさまざまな税金を納める義務があります。
主な税目は、法人住民税、法人事業税、消費税などです。
以下の表で、それぞれの税目の概要と特徴を整理します。
| 税目 | 課税主体 | 概要 |
|---|---|---|
| 法人住民税 | 都道府県・市区町村 | 法人住民税は、「均等割」と「法人税割」から構成されます。「均等割」は赤字でも必ず発生する最低税額で、自治体ごとに金額が異なります。 |
| 法人事業税 | 都道府県 | 事業税は会社の所得金額に応じて課される地方税です。資本金1億円以下で、所得が年2,500万円以下の場合は「外形標準課税」の対象外となります。 |
| 消費税 | 国税 | 開業から2年間はほとんどのマイクロ法人で免税事業者となりますが、売上や資本金により課税事業者となる場合があります。 |
さらに、印紙税(契約書や領収書などの規定金額以上の書類作成時)や源泉所得税(役員給与等に対して課税)も発生する場合があります。
このように、法人運営では多様な税目を適切に把握・管理することが重要です。
マイクロ法人の法人税はいくらかかるか
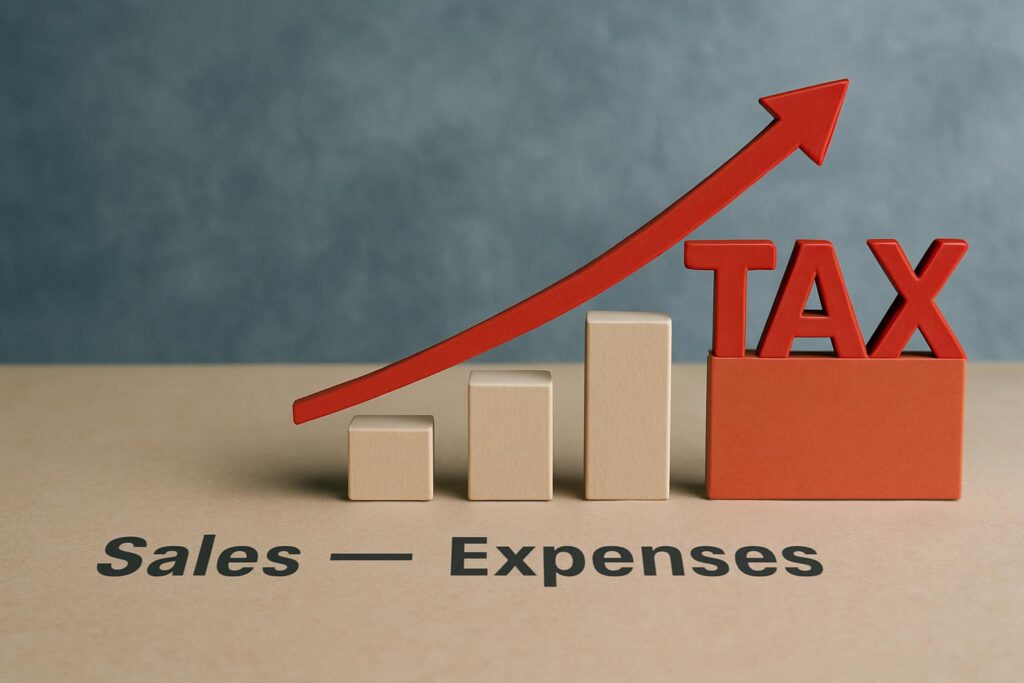
法人税率の解説と実質負担額
マイクロ法人にかかる法人税は、課税所得(=売上-経費)に対して税率をかけて算出されます。
中小企業に該当するマイクロ法人の場合、年800万円以下の所得には15%(2024年時点)、800万円を超える部分には23.2%の法人税率が適用されます。
また、ほとんどのマイクロ法人は所得が800万円以下となるため、実際の税負担は比較的少額ですが、税額控除や損金算入などにより実質負担額はさらに低くなるケースも多いです。
| 課税所得区分 | 法人税率 |
|---|---|
| 年800万円以下 | 15% |
| 年800万円超 | 23.2% |
なお、東日本大震災からの復興財源確保のため、法人税額には2.1%の復興特別法人税が上乗せされていましたが、2023年に廃止されています。
均等割りと利益が少ない場合の税負担
マイクロ法人はたとえ赤字や利益がほとんどなくても、最低限発生する税金として「法人住民税均等割り」があります。
これは資本金や従業員数に応じて自治体へ毎年納める必要があり、東京都の場合、資本金1,000万円以下、かつ従業員50人以下のマイクロ法人では年間7万円となります。
他の道府県や市町村でも同様の均等割りが定められており、利益ゼロでも必ず納税義務が生じる点に注意してください。
| 自治体 | 法人住民税 均等割り(基本額) |
|---|---|
| 東京都 | 70,000円/年 |
| 大阪府 | 50,000円/年 |
| 地方一般 | 50,000円/年 |
この均等割りは、税負担の最低ラインとして事業を休止していても支払いが必要となります。
利益別の法人税シミュレーション
利益ゼロの場合の実例
年間を通じて売上と経費が同額または赤字となり、法人としての所得がゼロの場合、法人税そのものはゼロ円となります。
しかし、法人住民税の均等割り(東京都なら年間7万円)および場合によっては法人事業税の最低額が発生するため、仮に収益がなかった場合でも合計7万円程度は毎年必要となります。
年間100万円、300万円の利益ケース
実際の利益額ごとの年間法人税等の目安は以下のようになります。
| 利益額 | 法人税 | 法人住民税 | 法人事業税 | 合計税額 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 70,000円 | 0円 | 70,000円 |
| 100万円 | 150,000円 | 約84,500円 | 約22,000円 | 約256,500円 |
| 300万円 | 450,000円 | 約164,500円 | 約66,000円 | 約680,500円 |
マイクロ法人の場合、利益が小さいうちは法人税負担が少額となります。
ただし、住民税や事業税も合算した総負担額でシミュレーション・計画を立てることが重要です。
こうした試算は税理士に相談し正確な額を算出することをおすすめします。
マイクロ法人の法人税額をシミュレーション

シミュレーションに必要な条件や前提
マイクロ法人の法人税額を具体的にシミュレーションするには、いくつかの前提条件を押さえておく必要があります。
まず、マイクロ法人の税負担は「所得金額(利益)」「所在地」「資本金額」「従業員数」などによって変わります。
このうち、一般的なマイクロ法人では「資本金1,000万円以下」「従業員1名(代表者のみ)」「東京都23区内に所在」「年間利益100万円〜300万円」を想定しやすいでしょう。
また、初年度でなければ均等割り(住民税の最低額)も必要です。
法人税の計算では、所得に対して課される「法人税」、地方税の「法人住民税(均等割/法人税割)」、「事業税」が主な税目です。
事業年度は1年(12カ月)で計算します。
具体的なシミュレーション例の紹介
ここでは、東京都(23区)に本店を置き代表者1人・資本金1,000万円以下のマイクロ法人で、利益が「ゼロ」「100万円」「300万円」の場合の法人税額や地方税額をシミュレーションします。
それぞれ、申告調整や特別控除は考慮せず、実務で想定される一般的な税率及び均等割のみを前提としています。
| シミュレーション条件 | 利益ゼロ | 利益100万円 | 利益300万円 |
|---|---|---|---|
| 法人税(15%) | 0円 | 約150,000円 | 約450,000円 |
| 法人住民税(均等割) | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 法人住民税(法人税割) | 0円 | 約13,500円 | 約40,500円 |
| 事業税(約6.7%) | 0円 | 約67,000円 | 約201,000円 |
| 合計税額 | 70,000円 | 約300,500円 | 約761,500円 |
マイクロ法人は、たとえ利益がなくても法人住民税の均等割(東京都の場合70,000円)が必ずかかります。
利益100万円、300万円の場合は法人税・事業税が課され、税金の合計は利益に比例して増加します。
法人税率は所得800万円以下の部分に対する軽減税率(15%)が適用され、これに基づき計算しています。
一方、「法人住民税」は均等割+法人税割で構成され、利益が出ると法人税割も発生します(東京都23区の場合)。
また「事業税」は、利益に対する約6.7%(中小法人の場合)のみ計上しています。
このシミュレーションから、マイクロ法人においても利益ゼロであれば最小限の税負担(均等割のみ)、利益が増えれば徐々に税額が増加する構造であることがわかります。
節税目的でマイクロ法人を活用する際は、年間利益がどれくらい出るかに応じて、維持コストも想定することが重要です。
マイクロ法人を活用するおすすめ方法

個人事業との税負担比較
マイクロ法人を設立する際に最も気になるのは、個人事業主として活動する場合と比較した税負担の違いです。
マイクロ法人では法人税等の優遇措置により、一定規模までなら税率が優遇されるため、所得が増えた場合に個人事業主より有利になることが多いです。
下記の表は、所得別に見る税負担のイメージです。
| パターン | 利益 | 所得税・住民税 (個人事業主) | 法人税・住民税 (マイクロ法人) |
|---|---|---|---|
| A | 100万円 | 約17万円 | 約7万円 |
| B | 300万円 | 約65万円 | 約20万円 |
| C | 500万円 | 約118万円 | 約34万円 |
利益が少額であれば法人設立のメリットは小さいですが、利益が年間100万円を超えてくると税率の差が大きくなり、マイクロ法人を活用することでトータルの税負担を抑制できます。
ただし、法人維持コスト(均等割りや会計サービス費用等)も加味した総合的判断が必要です。
社会保険加入のメリットとポイント
マイクロ法人にすることで社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じるため、「個人事業主の国民健康保険・国民年金より保障が手厚くなる」ことが大きなメリットです。
特に将来受け取る年金額や、家族への健康保険適用範囲が広がる点は魅力的です。
一方、「役員報酬」をいくらに設定するかが社会保険料負担額を大きく左右します。
役員報酬を最低賃金水準(月額8万円など)に抑えることで、社会保険料も低く抑えるスキームを活用するのが一般的です。
ただし、あまりに低額に設定すると将来の年金受取額に影響が出るため、将来設計も踏まえて報酬額を決めることがポイントです。
二拠点経営や副業活用の事例
マイクロ法人は「本業の会社員としての収入」とは別に、副業や資産管理を法人化することで節税・社会保険の最適化を図るケースによく使われています。
たとえばサラリーマンが不動産投資用の会社や、コンサル・講師業用の法人を設立するケースが典型です。
また地方と都市部などに事務所や拠点を置き、経費として交通費や家賃等を計上する「二拠点経営」もマイクロ法人での活用事例です。
拠点間の交通費や家賃、通信費などが法人の経費として計上できるため、節税につなげやすい特徴があります。
一方で、法人設立・運営の際には銀行口座の開設や経費計上のルール遵守が求められます。
個人資産と混同しないよう、明確な会計処理が必要です。
マイクロ法人の法人税対策で注意すること

税務調査や節税のリスク
マイクロ法人での法人税対策を講じる際には、過度な節税や形式的な取引は否認されるリスクがあるため、注意が必要です。
国税庁は、近年マイクロ法人の増加を背景に、個人所得の分散や社会保険料の軽減目的で設立された法人に対し、税務調査を強化しています。
明確な業務実態がなく、節税のみを目的とした法人形態は、法人税法上の「同族会社の行為計算否認規定」や、適正な所得配分が行われているかについて厳しくチェックされます。
また、個人と法人間での取引(例:自宅事務所の家賃や業務委託費)の金額設定が著しく相場とかけ離れている場合や、実態の伴わない経費計上などは、否認される可能性もあるため、適正な運用が必要です。
法人口座・会計処理・経費の留意点
マイクロ法人運営において、多くの経営者が見落としがちなのが、法人口座の分別管理や会計処理、経費計上ルールの徹底です。
法人と代表者個人の資金を混同して管理すると、税務調査で「プライベート経費の混在」とみなされる可能性が高まります。
| 注意が必要な会計処理 | 主なリスク・対策内容 |
|---|---|
| 法人口座と個人口座の混同 | 法人収入や支払いは必ず法人口座で行い、個人用としっかり分離する。 |
| 曖昧な経費計上 | 事業関連性を証明できる領収書を保管し、プライベート利用分は按分して計上。 |
| 現金管理の不備 | 帳簿と現金残高を定期的に照合し、不明点が生じないよう記録を厳重管理。 |
法人用のクレジットカードや支払専用口座を導入し、経費精算も規則に従い運用しましょう。
もしプライベートな出費を法人から支出した場合には、必ず「役員仮払金」や「役員報酬」として正しく会計処理することが大切です。
経費計上の根拠と証拠資料の管理
マイクロ法人においては、小規模ながらも税務上の経費計上は細心の注意が必要です。
経費として計上するには「業務の遂行に直接必要」であることと、「証拠となる資料」が必須です。
| 必要な証拠資料 | 具体的内容・保存期限の目安 |
|---|---|
| 領収書・請求書 | 宛名が法人名、内容の記載、取引日が明確であること。7年間保存が原則。 |
| 業務日報・会議資料 | 出張費や交際費の根拠として有効。費用発生の実態を証拠づける。 |
| 契約書・発注書 | 委託費や社外サービス利用の証明として必要。 |
インターネットバンキングの画面キャプチャや電子帳簿保存法に基づくデータ保存も認められていますが、正しい形式で保管することが不可欠です。
税務調査時に質問されても、明確に回答・説明できるよう資料を整理しておきましょう。
マイクロ法人設立前に知っておきたい情報

設立費用や手続きの流れ
マイクロ法人を設立する際には、必要な費用と一連の手続きの流れを正しく把握することが非常に重要です。
設立時に発生する主な費用には、定款認証手数料、登録免許税、印紙代、公証人役場での手数料などがあります。
以下の表では、マイクロ法人設立時に発生する代表的な費用項目を整理しています。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 約52,000円 | 株式会社のみ、公証人役場で認証 |
| 定款に貼付する印紙税 | 40,000円 | 電子定款なら不要 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 株式会社の場合。合同会社は60,000円 |
| 登記謄本や印鑑証明書の取得費 | 数千円程度 | 法務局で取得 |
| 専門家への報酬 | 依頼内容による | 税理士・司法書士等へ依頼時 |
マイクロ法人の設立手続きは、おおまかに次の流れとなります。
- 会社の定款(ルール)の作成および認証
- 必要書類の準備(設立登記申請書・印鑑届出書など)
- 資本金の払い込み
- 法務局で設立登記の申請
- 登記簿謄本や印鑑証明書を取得
- 税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出
- 社会保険の手続き(任意)
これらの手続きは自分で行うことも可能ですが、手続きミスによるやり直しや時間的コストを考え、司法書士や税理士などの専門家に依頼するケースも増えています。
専門家への相談のタイミングとポイント
マイクロ法人を設立する前には、税理士や社労士などの専門家に早目に相談することが成功のカギとなります。
特に税制や社会保険の取り扱いは将来の経営リスクや節税効果にも直結するため、事前に以下のような点を明確にしておくことが大切です。
- 事業内容や収益計画に適した法人形態(株式会社・合同会社)の選択
- 法人の役員報酬を含めた最適な所得分散方法
- 法人設立による社会保険への加入義務や負担を踏まえた総合的な損益シミュレーション
- 個人事業主や副業との兼業パターンにおける税務リスクと利益バランス
専門家への相談は、会社の設立内容が固まる前、すなわち検討段階から始めるのが理想的です。
設立後に制度や運営方法を見直すことは難しいため、疑問点や不安がある場合は早めにアドバイスを求めましょう。
また、マイクロ法人を利用した節税や社会保険加入の活用法においては、税務調査やコンプライアンス上の注意点も多いため、「最新の法改正情報」に基づいた専門家の意見を参考にしてください。
まとめ
マイクロ法人は、低コストかつ柔軟な運営が可能なため、節税や社会保険加入の選択肢として注目されています。
しかし、実際に法人税や各種税金、社会保険料、設立費用などトータルでのシミュレーションが不可欠です。
最適な活用には、税理士や社会保険労務士などの専門家への相談をおすすめします。




