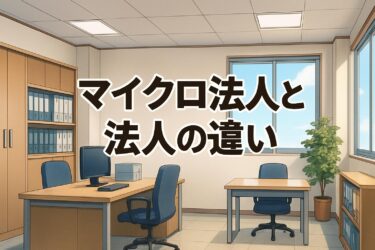マイクロ法人と個人事業主、どちらが手取りを最大化できるかお悩みではありませんか?
本記事では、最大の焦点である「社会保険料」と「税金」の違いを年収別シミュレーションで徹底比較します。
結論として、事業所得が一定額を超えると、社会保険料を最適化できるマイクロ法人が有利になります。
あなたに最適な選択肢がわかる診断チャートから、設立のタイミング、注意点まで全て解説するので、ぜひご自身の状況と照らし合わせてみてください。
マイクロ法人と個人事業主 結局どっちがお得?
「マイクロ法人と個人事業主、結局どっちを選べば一番手取りが増えるの?」
これは、事業を始める方や、事業が軌道に乗ってきた方の多くが抱える共通の悩みです。
結論から言うと、どちらか一方が絶対にお得ということはなく、あなたの事業所得(利益)や家族構成、将来の展望によって最適な選択は変わります。
個人事業主は、開業手続きが簡単で、利益を比較的自由に使える手軽さが魅力です。
一方、マイクロ法人は、設立に手間とコストがかかるものの、社会保険料や税金の面で大きなメリットを享受できる可能性があります。
この章では、まず両者の全体像を比較し、あなたがどちらのタイプに向いているのかを判断するための簡単な診断チャートをご用意しました。
まずはここで大まかな方向性を掴み、続く章で解説する具体的なシミュレーションや節税スキームを読み進めていきましょう。
| 比較項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 設立手続き・費用 | 定款認証や法人登記が必要。 約6万円~25万円の設立費用がかかる。 | 税務署に開業届を提出するだけ。 費用は原則0円。 |
| 税金 | 法人税・法人住民税・法人事業税など。 利益が少ないうちは税率が高いが、所得が増えると所得税より有利になる。 | 所得税・住民税・個人事業税など。 所得が増えるほど税率が上がる累進課税。 |
| 社会保険 | 社長1人でも加入義務あり。 厚生年金と健康保険に加入。保険料は会社と個人で折半。 | 従業員5人未満は加入義務なし。 国民年金と国民健康保険に加入。保険料は全額自己負担。 |
| 経費の範囲 | 役員報酬、退職金、生命保険料など、経費にできる範囲が広い。 | 事業に関連する費用のみ経費計上可能。 |
| 社会的信用度 | 法人格があるため、一般的に高い。 融資や取引で有利になる傾向がある。 | 法人に比べると一般的に低いと見なされることがある。 |
| 事務負担 | 複雑な法人決算が必要。 税理士への依頼が一般的でコストがかかる。 | 確定申告(青色申告・白色申告)を行う。 比較的シンプルで、自分でも対応可能。 |
| 赤字の場合 | 赤字でも法人住民税の均等割(最低約7万円)が発生する。 | 所得税・住民税は発生しない。 |
| 事業資金の自由度 | 会社のお金と個人のお金は明確に区別される。 役員報酬として受け取る必要があり、自由に使えない。 | 事業用の資金とプライベートの資金の区別が緩やかで、比較的自由に使える。 |
あなたの状況に合わせた選択診断チャート
まだ迷っているあなたへ。いくつかの質問に答えるだけで、どちらの選択肢がよりご自身の状況に合っているかのヒントが見つかります。
深く考えず、直感で答えてみてください。
- Q1. 年間の事業所得(売上から経費を引いた利益)が500万円を安定して超えそうですか?→
はい:マイクロ法人を検討する価値が十分にあります。特に所得が800万円を超えると、税率や社会保険料の面で法人化のメリットが大きくなる可能性が高いです。
いいえ:まずは個人事業主からスタートするのが手軽でおすすめです。事業が成長してから法人化を検討しましょう。 - Q2. 社会的信用度を高めて、銀行からの融資や大手企業との取引を有利に進めたいですか?→
はい:法人格を持つマイクロ法人が断然有利です。「株式会社」や「合同会社」という肩書は、ビジネスにおいて大きな信用力となります。
いいえ:個人向けのサービスが中心で、特に信用度を重視しない場合は、個人事業主で問題ありません。 - Q3. 経理や税務に関する事務作業は、できるだけシンプルに済ませたいですか?→
はい:個人事業主(特に青色申告)がおすすめです。会計ソフトを使えば、比較的簡単に確定申告ができます。
いいえ:マイクロ法人は決算申告が複雑なため、税理士への依頼が一般的です。専門家に任せるコストを許容できるなら問題ありません。 - Q4. 将来、自分自身や家族に退職金を支払うことを考えていますか?→
はい:マイクロ法人を設立すれば、役員退職金を経費として計上できます。退職金は税制上非常に優遇されており、大きな節税効果が期待できます。
いいえ:個人事業主でも小規模企業共済などで退職金に備えることは可能ですが、法人ほどの柔軟性や節税メリットはありません。 - Q5. 事業で得た利益は、すぐに生活費として自由に引き出したいですか?→
はい:個人事業主が向いています。事業用の口座からプライベートな支出をすることも比較的自由です。
いいえ:マイクロ法人では、会社のお金と個人のお金は厳格に区別されます。自分への給与(役員報酬)として計画的に受け取る必要があり、自由度は低くなります。
いかがでしたでしょうか?
この診断はあくまで一つの目安です。
あなたの心づもりがマイクロ法人に傾いたか、それとも個人事業主のままが良さそうだと感じたか、その感覚を大切にしながら、次の章で解説する具体的な手取り額のシミュレーションへと進んでいきましょう。
最大の焦点 節税と社会保険におけるマイクロ法人と個人事業主の違い

マイクロ法人と個人事業主のどちらを選ぶか考える上で、避けては通れないのが「社会保険」と「税金」の問題です。
この2つの負担額が、最終的な手取り額に最も大きな影響を与えます。
一見複雑に見えますが、仕組みを理解すれば、どちらが自分にとって有利なのかが見えてきます。
ここでは、両者の決定的な違いを分かりやすく解説します。
社会保険料の負担額はこんなに違う
事業で得た利益から必ず支払わなければならない社会保険料。
実は、マイクロ法人を設立する最大のメリットは、この社会保険料を合法的に最適化できる点にあると言っても過言ではありません。
個人事業主とマイクロ法人では、加入する制度そのものが異なり、負担額に雲泥の差が生まれます。
個人事業主が加入するのは「国民健康保険」と「国民年金」です。
国民健康保険料は前年の所得に応じて算出され、所得が増えれば増えるほど保険料も高くなります。
自治体によっては上限が年間100万円を超えるケースもあり、大きな負担となります。
また、国民健康保険には「扶養」という概念がないため、配偶者や子供がいる場合は、家族一人ひとりが保険料を支払う必要があります。
一方、マイクロ法人の役員は「健康保険(協会けんぽなど)」と「厚生年金保険」に加入します。
こちらの保険料は、事業の利益ではなく、法人から受け取る「役員報酬」の額(標準報酬月額)を基準に決まります。
つまり、役員報酬を低く設定することで、社会保険料の負担を大幅にコントロールできるのです。
さらに、健康保険には「扶養」の制度があるため、一定の収入以下の家族を扶養に入れることができ、家族分の追加保険料はかかりません。
将来受け取る年金額が国民年金のみの場合より手厚くなるというメリットもあります。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人(役員) |
|---|---|---|
| 加入する保険 | 国民健康保険 + 国民年金 | 健康保険(協会けんぽ等) + 厚生年金保険 |
| 保険料の基準 | 前年の事業所得など | 役員報酬額(標準報酬月額) |
| 保険料のコントロール | 困難(所得に連動) | 容易(役員報酬額で調整可能) |
| 扶養制度 | なし | あり(配偶者や子供を扶養に入れられる) |
| 将来の年金 | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 |
税金の支払額に影響する控除と経費の違い
税金の仕組みも、個人事業主とマイクロ法人では大きく異なります。
個人事業主の利益には「所得税」や「住民税」が直接課せられますが、法人の利益には「法人税」がかかり、役員個人は受け取った役員報酬に対して「所得税」や「住民税」を支払います。
この構造の違いが、節税効果の差を生み出します。
特に注目すべきは「控除」の違いです。個人事業主は、青色申告を行うことで最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。
一方、マイクロ法人から役員報酬を受け取る場合、その報酬は「給与所得」扱いとなり、実際の経費がなくても収入に応じて一定額が自動的に差し引かれる「給与所得控除」が適用されます。
この給与所得控除は、最低でも55万円あり、役員報酬額が増えれば控除額も大きくなるため、青色申告特別控除よりも有利になるケースが多くあります。
また、経費として認められる範囲にも違いがあります。マイクロ法人では、個人事業主よりも経費として計上できる項目が広がる傾向にあります。
- 生命保険料:法人契約の生命保険は、保険の種類によって支払保険料の全額または一部を損金(法人の経費)に算入できます。個人事業主の生命保険料控除(所得控除)よりも節税効果が高くなる場合があります。
- 出張手当(日当):出張旅費規程を整備すれば、役員に対して出張手当を支給できます。この手当は法人の経費となり、受け取った役員個人にとっては非課税所得となるため、非常に有効な節税策です。
- 役員社宅:法人が借り上げた物件を役員に貸し出す「役員社宅」の制度を使えば、家賃の大部分を法人の経費にできます。個人の住居費負担を大幅に軽減しながら節税が可能です。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 利益にかかる主な税金 | 所得税、住民税、個人事業税 | 法人税、法人住民税、法人事業税 |
| 個人に適用される主な控除 | 青色申告特別控除(最大65万円)など | 給与所得控除(最低55万円〜)など |
| 経費にできる範囲の例 | 事業に直接必要な費用 | 事業費に加え、役員社宅の家賃、出張手当、法人契約の生命保険料など、より広い範囲で経費化が可能 |
【年収別シミュレーション】マイクロ法人と個人事業主の手取り額の違いを比較

「結局、自分はどっちを選べばいいの?」という疑問に答えるため、ここでは事業所得(売上から経費を差し引いた利益)別に、個人事業主とマイクロ法人の手取り額がどのように変わるのかを具体的にシミュレーションします。
どちらがより多くの資金を手元に残せるのか、その分岐点を探っていきましょう。
※以下のシミュレーションは、特定の条件下での試算です。実際の手取り額は、お住まいの地域、家族構成、加入する健康保険組合、経費の内容などによって変動します。あくまで目安としてご活用ください。
【シミュレーションの前提条件】
- 対象者:東京都内在住、40歳未満(介護保険第2号被保険者ではない)、独身・扶養家族なし
- 個人事業主:青色申告(65万円控除)を適用。国民健康保険・国民年金に加入。
- マイクロ法人:役員報酬を月額5万円(年額60万円)に設定。協会けんぽ・厚生年金に加入。法人の利益はすべて内部留保。
- 所得控除:基礎控除、社会保険料控除のみを考慮。
- 税率等:2023年時点の税率・保険料率を元に計算。復興特別所得税も考慮。
- 手取り額の定義:
- 個人事業主:事業所得 – (所得税 + 住民税 + 社会保険料)
- マイクロ法人:(役員報酬 – 社会保険料個人負担分) + (法人利益 – 法人税等 – 社会保険料法人負担分) ※個人の税金は0円と仮定
事業所得300万円の場合
まずは、フリーランスとして独立した直後などに想定される事業所得300万円のケースです。
この段階では、まだ大きな売上が見込めていない状況と言えるでしょう。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
| 社会保険料 | 約430,000円 | 約170,000円(個人・法人合計) |
| 税金(所得税・住民税・法人税等) | 約180,000円 | 約550,000円 |
| 最終的な手取り額 | 約2,390,000円 | 約2,280,000円 |
事業所得が300万円の段階では、個人事業主の方が手取り額が多くなる傾向にあります。
マイクロ法人は社会保険料を大幅に抑えられますが、法人設立の初期費用や維持コスト(法人住民税均等割など)、そして法人税の負担があるため、トータルで見ると個人事業主に軍配が上がります。
この所得帯では、まず個人事業主として事業を軌道に乗せることを優先するのが賢明と言えるでしょう。
事業所得500万円の場合
次に、事業が安定し、所得が500万円に達したケースを見てみましょう。
このあたりから、税金や社会保険料の負担が重く感じ始める方が増えてきます。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 5,000,000円 | 5,000,000円 |
| 社会保険料 | 約670,000円 | 約170,000円(個人・法人合計) |
| 税金(所得税・住民税・法人税等) | 約590,000円 | 約1,000,000円 |
| 最終的な手取り額 | 約3,740,000円 | 約3,830,000円 |
事業所得500万円が、まさに損益分岐点と言えるでしょう。
このシミュレーションでは、マイクロ法人の手取り額が個人事業主をわずかに上回りました。
個人事業主は所得の増加に伴い、累進課税である所得税と、上限が高い国民健康保険料の負担が急激に増大します。
一方、マイクロ法人は役員報酬を低く抑えることで社会保険料を固定し、超過分を税率の低い法人税で納めるため、トータルでの負担を軽減できるのです。
法人化を検討し始めるのに適したタイミングと言えます。
事業所得800万円の場合
最後に、事業が大きく成長し、所得が800万円に達したケースです。
ここまで来ると、節税対策が手取り額に与える影響は非常に大きくなります。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 8,000,000円 | 8,000,000円 |
| 社会保険料 | 約900,000円(上限付近) | 約170,000円(個人・法人合計) |
| 税金(所得税・住民税・法人税等) | 約1,500,000円 | 約1,700,000円 |
| 最終的な手取り額 | 約5,600,000円 | 約6,130,000円 |
事業所得800万円のレベルでは、その差は歴然です。マイクロ法人の方が個人事業主よりも手取り額が年間で約50万円以上も多くなりました。
個人事業主の場合、所得税率は23%に達し、社会保険料もほぼ上限に張り付きます。所得の約30%が税金と社会保険料で引かれてしまう計算です。
対してマイクロ法人は、社会保険料を低額に維持しつつ、法人税(所得800万円以下の部分は軽減税率が適用)で納税するため、手元に多くのキャッシュを残すことが可能になります。
この所得水準であれば、マイクロ法人設立のメリットを最大限に享受できると言えるでしょう。
マイクロ法人設立による節税スキームを徹底解説

マイクロ法人を設立する最大の目的は、多くの場合「節税」です。
個人事業主の「事業所得」を、マイクロ法人からの「給与所得」や「役員報酬」に変えることで、様々な税制上のメリットを享受できます。
ここでは、マイクロ法人だからこそ活用できる代表的な3つの節税スキームを、具体的な仕組みとともに詳しく解説します。
役員報酬と給与所得控除の活用
マイクロ法人設立による節税の根幹をなすのが、「給与所得控除」の活用です。
これは、個人事業主にはない、給与所得者特有の強力な控除制度です。
個人事業主の場合、所得は「売上 − 必要経費 = 事業所得」として計算されます。
一方、マイクロ法人を設立し、自分自身に役員報酬を支払うと、その所得は「給与所得」として扱われます。
給与所得は「収入金額(役員報酬額) − 給与所得控除額」で計算されます。
この「給与所得控除」は、サラリーマンのスーツ代や書籍代のような、仕事に必要な経費を概算で認めるもので、実際に経費を使っていなくても収入に応じて自動的に差し引かれます。
つまり、個人事業主として経費計上していたものとは別に、二重で経費のような控除を受けられる点が大きなメリットです。
給与所得控除額は、年収に応じて以下のように定められています。
| 給与等の収入金額 (年収) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 |
| 162.5万円超 180万円以下 | 収入金額 × 40% − 10万円 |
| 180万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円 (上限) |
例えば、年間500万円の所得がある場合を考えてみましょう。個人事業主であれば、500万円がそのまま事業所得(各種控除前)となります。
しかし、マイクロ法人から役員報酬として500万円を受け取ると、上の表から「500万円 × 20% + 44万円 = 144万円」が給与所得控除として差し引かれます。
その結果、課税対象となる所得を356万円まで圧縮できるのです。
この差が、所得税や住民税の節税に直結します。
家族への給与支払いで所得を分散
所得税は、所得が高くなるほど税率も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
そのため、一人に所得が集中するよりも、家族に所得を分散させた方が、世帯全体で支払う税金を抑えられます。
個人事業主の場合、家族に給与を支払うには「青色事業専従者給与」の届出が必要で、事業に専従していることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
一方、マイクロ法人では、家族を役員(非常勤でも可)や従業員とすることで、業務の実態に応じて給与を支払うことが比較的容易になります。
例えば、社長一人が800万円の役員報酬を受け取るケースと、社長が500万円、配偶者を非常勤役員として300万円の役員報酬を支払うケースを比較してみましょう。
後者の場合、社長と配偶者のそれぞれに給与所得控除や基礎控除が適用されるため、一人で800万円を受け取るよりも世帯全体での課税所得を低く抑えることができます。
結果として、所得税・住民税の合計額が安くなるのです。
ただし、注意点として、家族への給与支払いは、その役職や業務内容に見合った常識的な金額でなければなりません。
業務の実態が全くないにもかかわらず給与を支払うと、税務調査で否認されるリスクがあるため、議事録の作成や業務内容の記録など、実態を証明できる準備をしておくことが重要です。
退職金制度(小規模企業共済など)の活用
将来の備えをしながら、現在の税負担を軽減できるのが退職金制度の活用です。
マイクロ法人を設立すると、経営者自身が退職金を受け取る準備をすることができ、これは税制上非常に優遇されています。
退職金は「退職所得」として扱われ、他の所得(給与所得や事業所得)とは別に税額が計算されます。
退職所得には、長年の功労に報いるという観点から、「退職所得控除」という大きな控除枠があり、さらに控除後の金額を1/2にしてから税率をかけるため、税負担が大幅に軽減されます。
マイクロ法人の経営者が活用できる代表的な退職金準備制度には、以下のようなものがあります。
- 役員退職慰労金
法人の利益を原資として内部で積み立て、退職時に経営者に支払う制度です。適正な金額であれば、法人の経費(損金)として計上できるため、法人税の節税につながります。そして受け取る側は、税制上優遇された退職所得として受け取れます。 - 小規模企業共済
個人事業主や小規模な会社の役員が加入できる、国が作った退職金制度です。毎月の掛金(最大7万円)は、全額が個人の所得から控除(小規模企業共済等掛金控除)されます。これにより、所得税・住民税を直接的に減らす効果があります。将来、共済金を受け取る際も、退職所得または公的年金等雑所得として扱われ、税制上有利です。 - iDeCo(個人型確定拠出年金)
役員個人として加入できる私的年金制度です。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税です。受け取る際も退職所得控除や公的年金等控除の対象となります。
これらの制度を組み合わせることで、法人の利益を圧縮しつつ、個人の所得税・住民税も軽減し、さらに将来の資産形成を税制上有利に進めるという、一石三鳥の効果が期待できるのです。
事業運営におけるマイクロ法人と個人事業主の違い

節税や社会保険料だけでなく、日々の事業運営においてもマイクロ法人と個人事業主には大きな違いが存在します。
特に「社会的信用度」「資金調達のしやすさ」「会計・税務の事務負担」は、事業の成長性や日々の業務に直接影響を与える重要なポイントです。
ここでは、運営面での具体的な違いを詳しく比較・解説していきます。
社会的信用度と資金調達
事業を拡大していく上で、取引先や金融機関からの「信用」は不可欠な要素です。
法人格の有無は、この信用度に大きく影響します。
一般的に、個人事業主よりも法人のほうが社会的信用度は高いと評価されます。
法人は、法務局に設立登記を行うことで会社情報が公開され、誰でもその存在を確認できるためです。
これにより、取引先は安心して契約を結びやすく、特に大企業との取引(BtoB)では、契約の条件として法人格を求められるケースも少なくありません。
この信用度の差は、資金調達の場面でも顕著に現れます。
金融機関からの融資審査において、法人は事業と個人の資産が明確に分離されているため、事業計画や財務状況の透明性が高いと判断されやすい傾向にあります。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」をはじめ、法人を対象とした融資制度は豊富に用意されています。
一方、個人事業主は事業と個人の区別が曖昧に見られがちで、融資審査が厳しくなることがあります。
もちろん個人事業主向けの融資制度もありますが、選択肢の広さや融資限度額の面では法人に軍配が上がることが多いのが実情です。
| 項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 社会的信用度 | 高い(登記情報により客観的に証明可能) | 法人に比べると低いと見なされがち |
| 取引先の反応 | BtoB取引で有利。法人格を条件とする企業とも取引可能 | 取引に支障はないことが多いが、大企業との取引では不利になる場合も |
| 銀行口座 | 法人名義の口座を開設可能 | 個人名義または屋号付きの個人口座 |
| 資金調達 | 法人向けの融資制度が豊富で、審査上有利になる傾向。出資による資金調達も可能 | 利用できる融資制度が限定される場合がある。事業と個人の資産の区別がつきにくく審査が厳しくなることも |
会計・税務の事務負担とコスト
事業運営に欠かせない会計処理や税務申告は、マイクロ法人と個人事業主でその複雑さとコストが大きく異なります。
日々の業務負担や専門家へ支払う費用に直結するため、事前にその違いを正確に理解しておくことが重要です。
個人事業主の確定申告(青色申告・白色申告)
個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算し、原則として翌年の2月16日から3月15日までに「確定申告」を行う必要があります。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
- 白色申告:簡易な帳簿付けで済むため手軽ですが、税制上の特典は特にありません。
- 青色申告:複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の作成が必要ですが、最大65万円の青色申告特別控除や、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与、赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除など、大きな節税メリットがあります。
現在では会計ソフトが充実しているため、簿記の知識がなくても青色申告(65万円控除)の要件を満たす帳簿を作成することは十分に可能です。
事務負担は法人に比べて軽く、税理士に依頼する場合の費用も比較的安価に抑えられます。
マイクロ法人の決算申告
マイクロ法人は、定款で定めた事業年度(通常は1年間)が終了した後、原則として2ヶ月以内に「決算申告」を行う義務があります。
この手続きは個人事業主の確定申告よりもはるかに複雑です。
提出する書類は、法人税申告書に加え、決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書など多岐にわたります。
会計処理も個人事業主より厳格で、株主総会の開催や議事録の作成・保管といった会社法に基づいた手続きも必要になります。
この税務申告の複雑さから、ほとんどのマイクロ法人は税理士と顧問契約を結び、決算申告を依頼しています。
そのため、税理士への顧問料や決算料として、年間で数十万円のコストが発生するのが一般的です。
設立時にも定款認証や登記費用で20万円以上の実費がかかる点も考慮に入れる必要があります。
| 項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 申告の種類 | 決算申告(法人税、法人住民税、法人事業税など) | 確定申告(所得税、住民税、個人事業税など) |
| 申告時期 | 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 | 原則、翌年2月16日~3月15日 |
| 帳簿の複雑さ | 非常に複雑(複式簿記が必須で、会計処理も厳格) | 青色申告(複式簿記)でも会計ソフトで対応しやすい |
| 専門家への依頼 | 税理士への依頼が一般的(必須に近い) | 自分で行うことも可能。依頼する場合の費用は法人より安い |
| 年間コスト目安 (専門家依頼時) | 顧問料・決算料で年間20万円~ | 確定申告料で年間5万円~ |
個人事業主からマイクロ法人へ移行するベストなタイミング

個人事業主として事業が軌道に乗ってくると、多くの人が「法人成り」を意識し始めます。
しかし、どのタイミングでマイクロ法人へ移行するのが最もメリットが大きいのでしょうか。
タイミングを誤ると、かえって税負担や事務コストが増えてしまう可能性もあります。
ここでは、節税効果が最大化される具体的な2つのタイミングを詳しく解説します。
ご自身の事業状況と照らし合わせながら、最適な移行時期を見極めましょう。
課税所得が900万円を超えるとき
法人化を検討する最も代表的なタイミングが、個人事業主としての「課税所得」が900万円を超えたときです。
これは、個人に課される「所得税」と法人に課される「法人税」の税率構造の違いに起因します。
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」が採用されています。
一方、法人税は資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円を境に税率が二段階に分かれているだけで、個人のように税率が青天井に上がることはありません。
以下の表で、所得税と法人税の税率を比較してみましょう。
| 区分 | 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得税(個人) | 195万円超 ~ 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 ~ 695万円以下 | 20% | |
| 695万円超 ~ 900万円以下 | 23% | |
| 900万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% | |
| 1,800万円超 ~ 4,000万円以下 | 40% | |
| 4,000万円超 | 45% | |
| ※上記は一例です。実際には復興特別所得税などが加わります。 | ||
| 法人税(中小法人) | 年800万円以下の部分 | 15% |
| 年800万円超の部分 | 23.2% | |
| ※資本金1億円以下の中小法人等の場合。 | ||
表を見ると、課税所得が900万円を超えると、所得税率は33%になります。
一方で、法人税率は所得800万円超の部分でも23.2%です。
この税率の逆転現象が起こる「課税所得900万円」が一つの大きな目安となります。
マイクロ法人を設立し、自身への役員報酬を調整することで、個人にかかる高い所得税率を回避し、法人税の低い税率の恩恵を受けることが可能になるのです。
もちろん、社会保険料の負担なども考慮する必要がありますが、税率差による節税効果は非常に大きいと言えるでしょう。
消費税の課税事業者になるとき
もう一つの重要なタイミングは、消費税の納税義務が発生する「課税事業者」になるときです。
個人事業主は、原則として2年前(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年から消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。
このタイミングでマイクロ法人を設立すると、大きな節税メリットが生まれます。
なぜなら、新しく設立された法人は、原則として設立から最大2年間、消費税の納税が免除されるからです(資本金1,000万円未満などの要件あり)。
個人事業主としての売上実績は、新設法人には引き継がれません。
そのため、個人事業主として課税事業者になるタイミングで事業を法人へ移行(法人成り)することで、消費税の納税を合法的に先送りできるのです。
例えば、2024年の課税売上高が1,200万円だった個人事業主は、2026年から課税事業者になります。
しかし、2025年末で個人事業を廃業し、2026年1月からマイクロ法人として事業を開始すれば、2026年と2027年の2年間は消費税の免税事業者でいられる可能性があります。
また、近年導入されたインボイス制度の影響で、売上1,000万円以下でも取引先との関係上、あえて課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択するケースも増えています。
このような場合でも、法人化によって免税期間を確保できるメリットは同様に享受できるため、法人設立を検討する有力なきっかけとなります。
マイクロ法人設立前に知っておきたい注意点

マイクロ法人は、節税や社会保険料の最適化において大きなメリットがありますが、設立・運営には個人事業主にはないデメリットや注意点が存在します。
メリットだけに目を奪われず、これから解説する注意点を十分に理解した上で、法人化を検討することが重要です。
設立・維持にコストがかかる
個人事業主は開業届を提出するだけで事業を開始できますが、法人は設立するだけでも費用がかかり、事業を維持していくためのランニングコストも発生します。
設立時の初期費用(法定費用)
法人を設立するには、定款認証や登記申請が必要となり、法律で定められた費用(法定費用)がかかります。
主な費用は以下の通りで、最低でも合同会社で約6万円、株式会社で約20万円の実費が必要です。
これに加えて、司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合は別途報酬が発生します。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要 |
| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 0円 | 資本金の額による |
| 登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ | 資本金の0.7%(最低額) |
| 合計(電子定款の場合) | 約202,000円~ | 約60,000円~ | 定款謄本代などが別途必要 |
赤字でも発生する法人住民税均等割
個人事業主の場合、所得が赤字であれば所得税や住民税はかかりません。
しかし、法人の場合は、たとえ事業が赤字であっても、法人住民税の「均等割」という税金を毎年支払う義務があります。
これは、法人が所在する地方自治体に対して支払う会費のようなもので、資本金の額や従業員数によって金額は異なりますが、最低でも年間約7万円の負担が発生します。
これはマイクロ法人にとって無視できない固定コストです。
税理士など専門家への報酬
法人の会計処理や税務申告は、個人事業主の確定申告に比べて格段に複雑になります。
会計帳簿の作成基準が厳しく、提出すべき書類も多岐にわたるため、多くのマイクロ法人が税理士に顧問や決算申告を依頼しています。
その場合、月々の顧問料や決算申告料がランニングコストとして発生することも念頭に置いておく必要があります。
お金の使い方が厳しく制限される
個人事業主と法人の最も大きな違いの一つが、事業用資金の扱いです。
法人は法律上の「人格」を持つため、会社のお金と経営者個人のお金は厳格に区別しなければなりません。
会社のお金を自由に使えなくなる
個人事業主の場合、事業用の口座から生活費を引き出すことは比較的自由に行えます。
しかし、法人の場合、会社の口座にあるお金はあくまで「会社のもの」であり、社長が個人的な目的で自由に引き出すことはできません。
もし引き出した場合、「役員貸付金」として扱われ、会社に対して利息を支払う必要が生じます。
また、役員貸付金が多いと金融機関からの信用が低下し、融資審査で不利になる可能性もあります。
役員報酬は年に一度しか変更できない
社長個人が会社からお金を受け取る方法は、原則として「役員報酬」となります。
この役員報酬は、節税の観点から経費として認められるために「定期同額給与」というルールに従う必要があります。
これは、事業年度開始から3ヶ月以内に決定した金額を、その事業年度が終わるまで毎月同額で支払い続けなければならないというものです。
そのため、期の途中で業績が好調になったからといって急に報酬を増やしたり、逆に資金繰りが厳しくなったからといって減らしたりすることは原則としてできません。
資金計画を慎重に立てる必要があります。
事務手続きの負担が増加する
法人を設立すると、社会保険の手続きや会計・税務に関する事務負担が大幅に増加します。
社会保険の加入手続きと毎月の事務
法人を設立した場合、たとえ社長一人だけの会社であっても、健康保険と厚生年金保険(社会保険)への加入が法律で義務付けられています。
設立時には年金事務所などで加入手続きが必要となり、その後は毎月の役員報酬から社会保険料を計算し、会社負担分と合わせて納付する事務作業が発生します。
この手続きを怠ると、遡って保険料を請求されるなどのペナルティがあるため注意が必要です。
複雑な法人決算と申告
個人事業主の青色申告も複式簿記が必要ですが、法人の決算申告はさらに複雑です。
法人税申告書をはじめ、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書など、作成・提出すべき書類が非常に多くなります。
これらの書類をすべて自力で作成するのは専門知識がないと困難であり、多くの時間と労力を要します。
廃業の手続きが煩雑で費用もかかる
事業を始めることだけでなく、「やめること」のハードルが高いのも法人の特徴です。個人事業主であれば「廃業届」を税務署に提出するだけで済みますが、法人の場合はそう簡単にはいきません。
会社をたたむには、株主総会での解散決議、解散・清算人の登記、官報公告、債権の取り立てと債務の弁済、残余財産の分配、そして最後に清算結了の登記といった、多くの法的手続きを踏む必要があります。
これらの手続きには、登録免許税などの実費だけで数万円、司法書士などの専門家に依頼すればさらに数十万円の費用がかかることもあります。
まとめ
マイクロ法人と個人事業主のどちらが有利かは、事業所得の金額によって異なります。
最大の判断材料は社会保険料の負担額で、マイクロ法人は役員報酬と給与所得控除を上手く活用することで、個人事業主よりも手取り額を増やせる可能性があります。
一般的に課税所得が900万円を超えるタイミングが法人化を検討する一つの目安です。
ただし、法人には赤字でも発生する法人住民税均等割などのコストも存在します。
本記事のシミュレーションを参考に、ご自身の状況に合わせた最適な選択をしましょう。